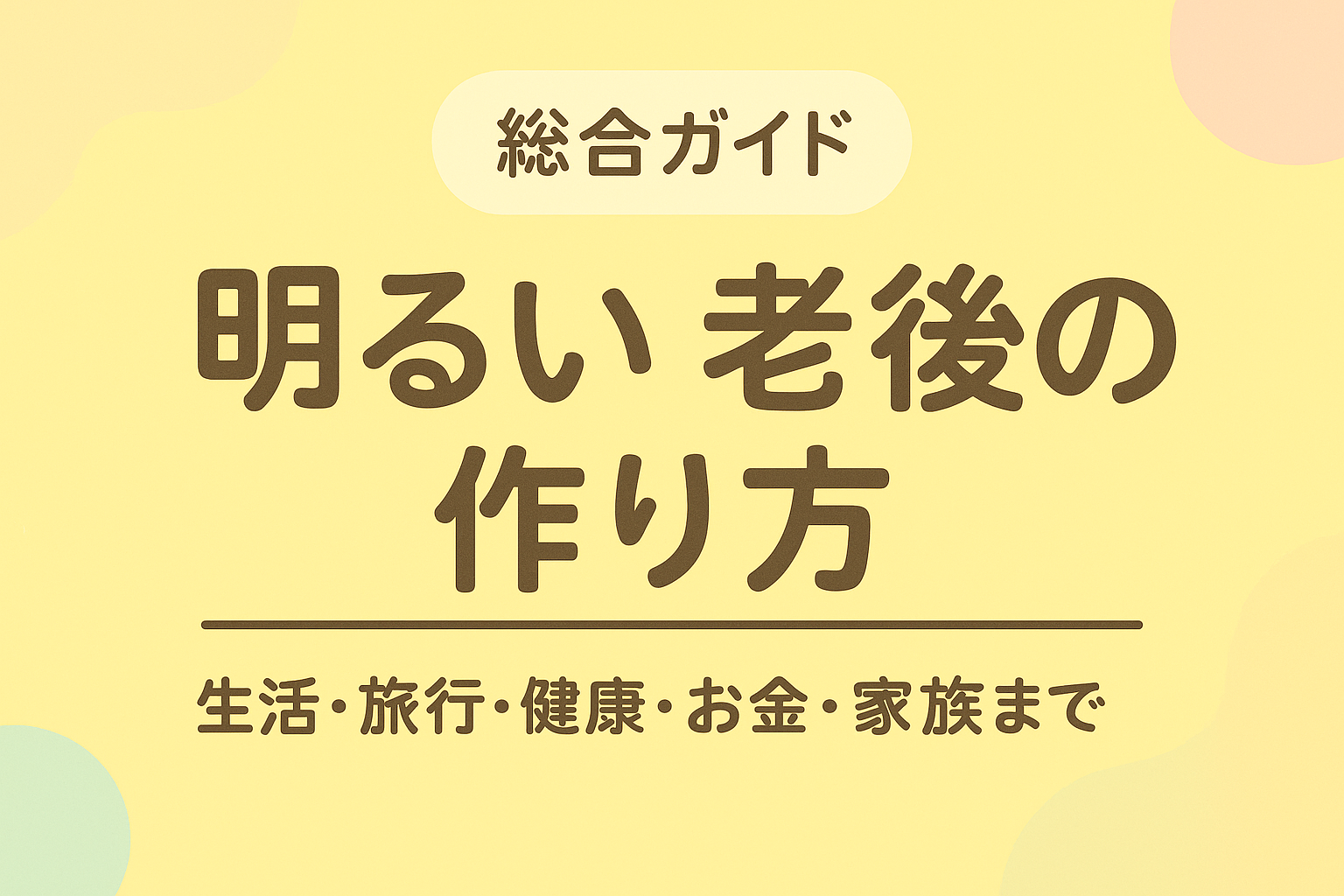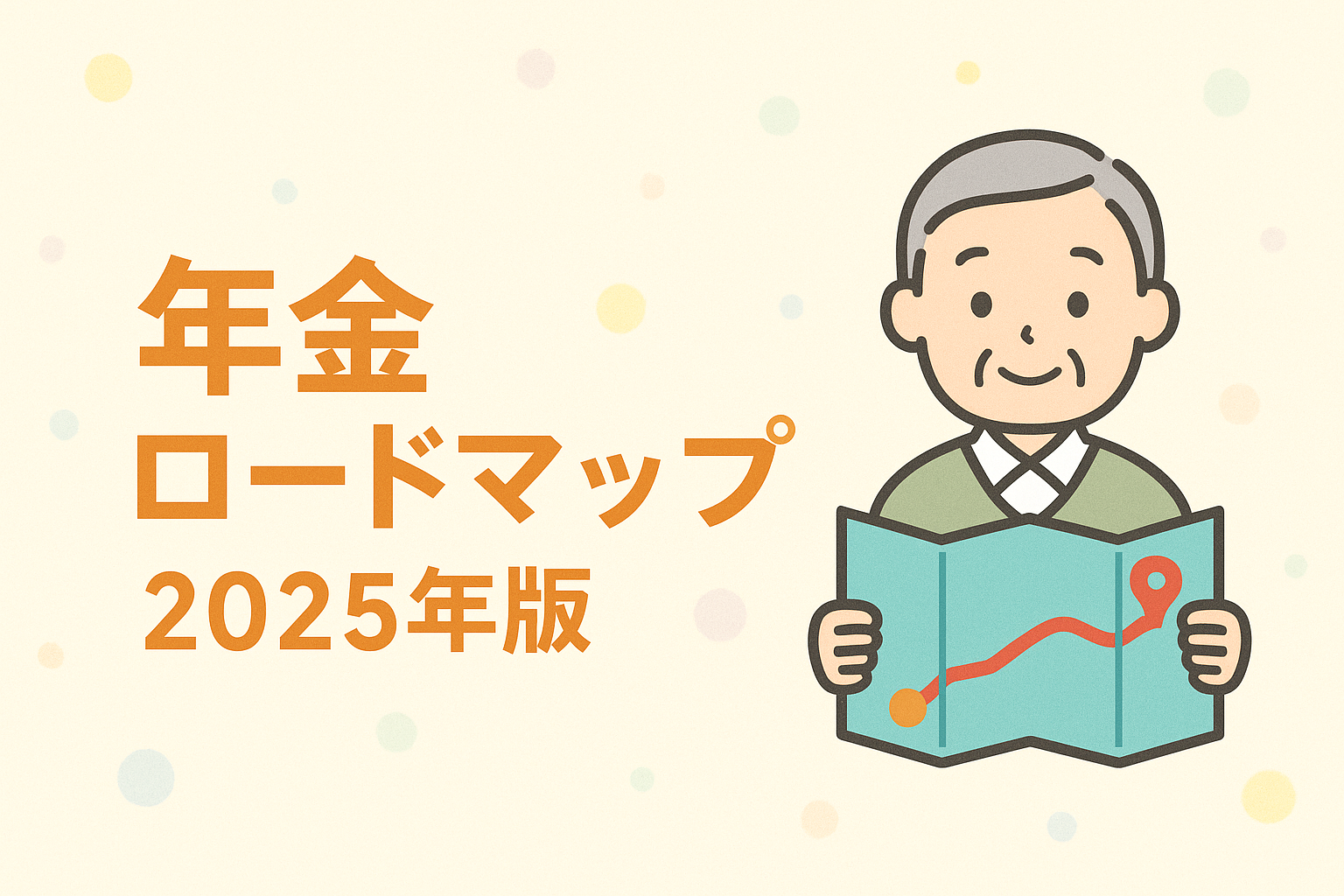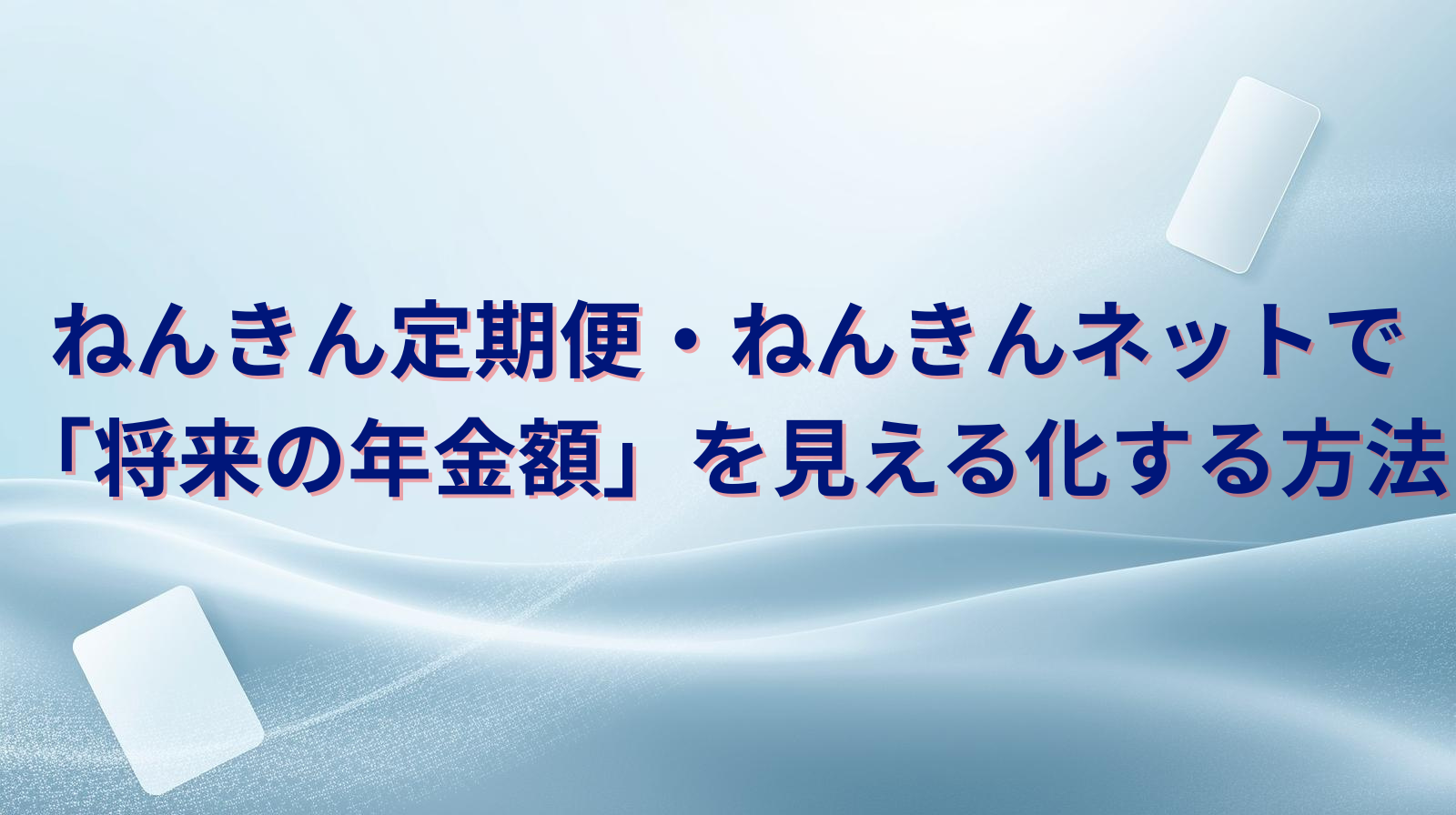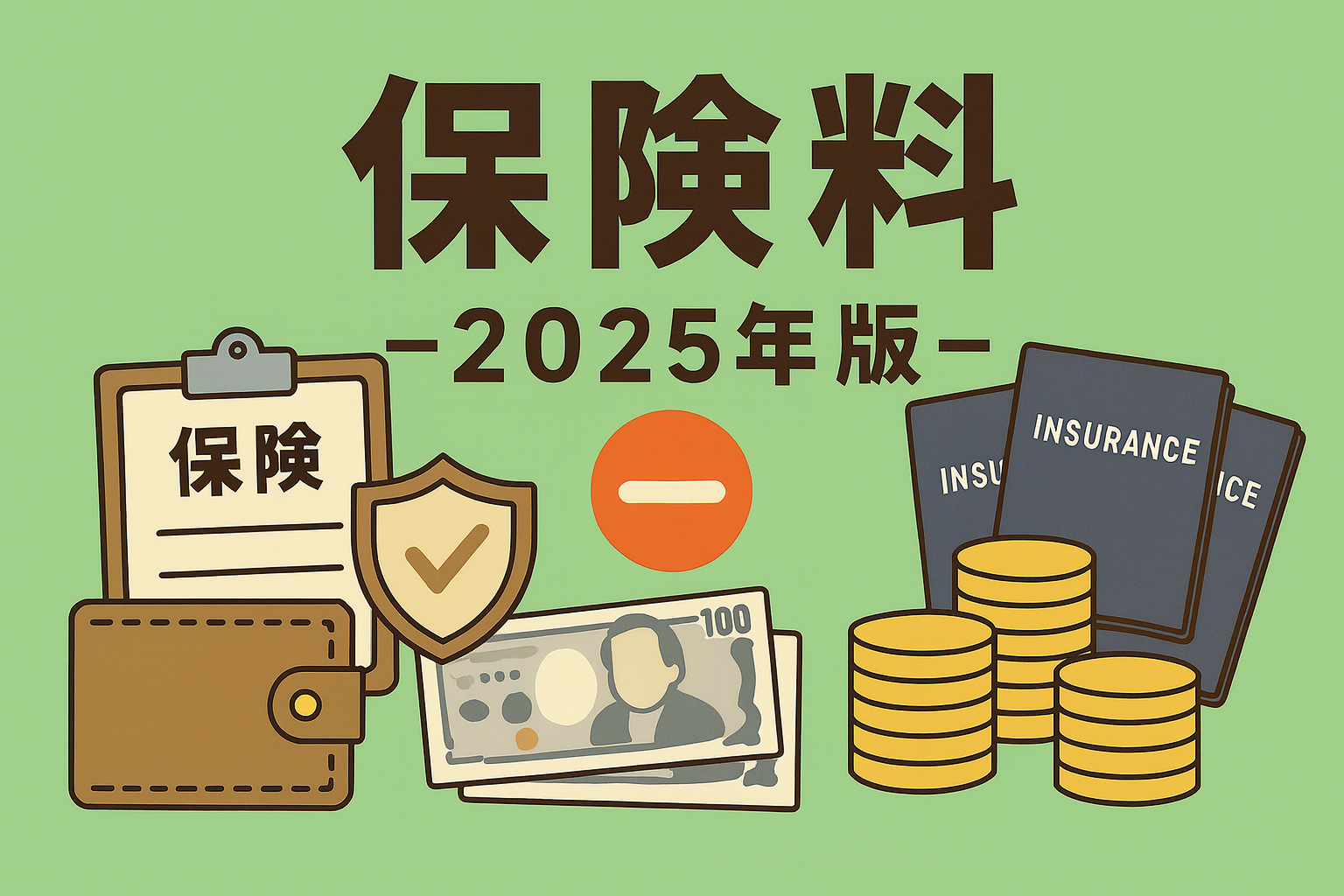ハウスリースバックってどうなの?|老後の資金と住まいを両立させる基礎知識
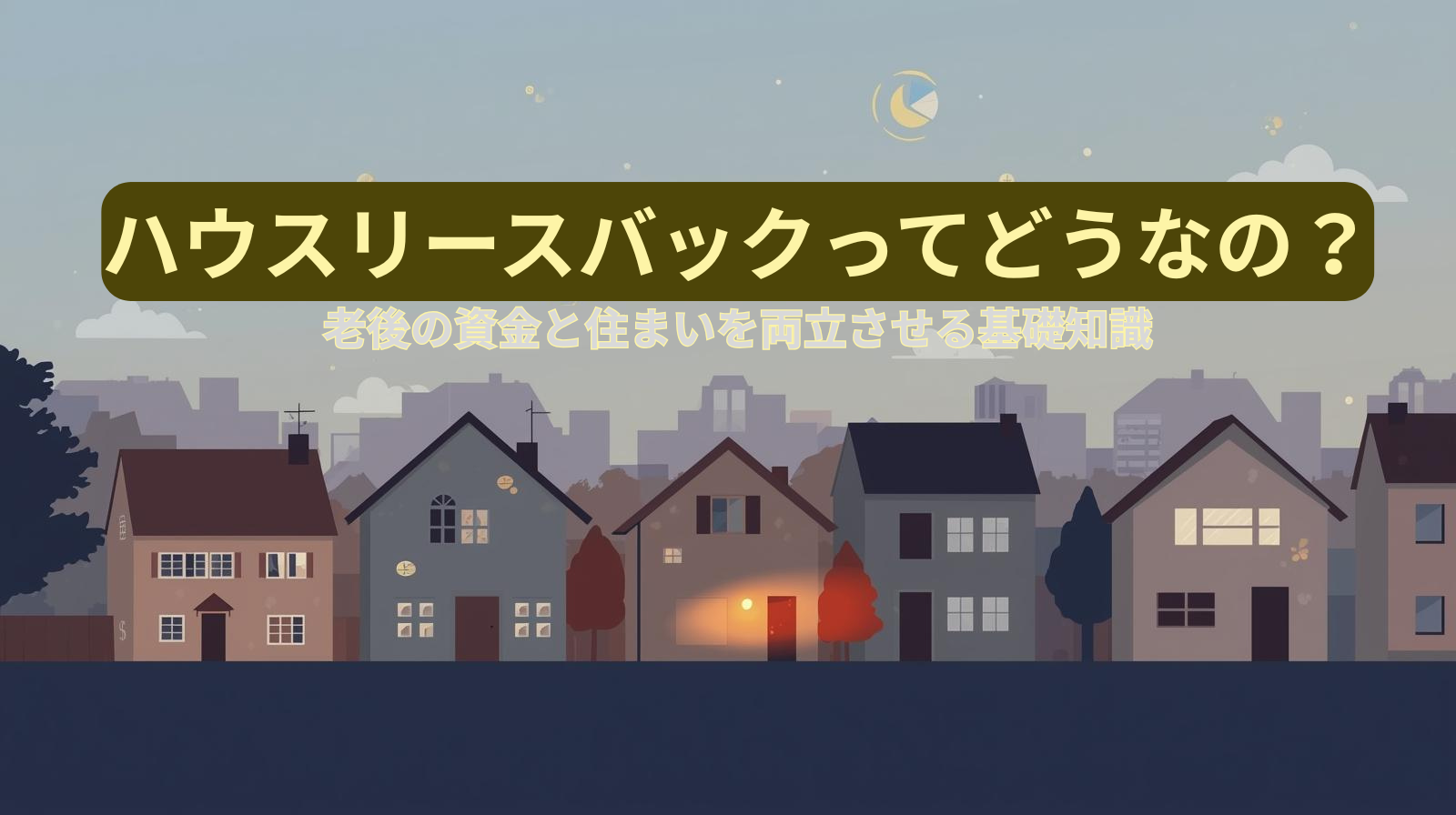
「家は手放したくないけれど、老後のお金も心配…」
そんなときに耳にするのが、ハウスリースバック(住宅リースバック)です。自宅をいったん売却し、買主と賃貸契約を結ぶことで、まとまったお金を受け取りつつ、同じ家に住み続けられるというしくみです。
一見とても便利ですが、契約内容をよく理解しないまま進めると、家賃が払えなくなったり、退去を求められたりするリスクもあります。国民生活センターでも、高齢者の相談件数がここ数年増えていると注意喚起されています。参考:国民生活センター「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!」
この記事でわかること・老後とどう関わる?
- ハウスリースバック(住宅リースバック)の基本的なしくみ
- 老後に利用される主な理由(メリット)と、見落としがちなデメリット
- リバースモーゲージ・通常の売却との違い
- 相続対策になるのか・売却時の所得税はどうなるのか
- 「契約者を子どもに変えられる?」「何年住まないといけない?」「途中解約できる?」といった実務的な疑問
- 老後の住まいとお金を考えるうえで、リースバックをどう位置づければよいか
老後の生活設計では、「住み慣れた家にどこまで住み続けるか」と「資金をどう確保するか」が大きなテーマになります。ハウスリースバックは、その2つを同時に考えるときの選択肢のひとつとして知っておきたい制度です。
ただし、誰にでもおすすめできる魔法の方法ではありません。この記事では、良いところとリスクをバランスよく整理し、「自分のケースで使うかどうか」を判断するための土台をつくることを目指します。
1.ハウスリースバック(住宅リースバック)とは?
1-1.基本のしくみ
ハウスリースバックは、一般に次のような流れで行われます。
- 自宅(戸建て・マンション)をリースバック事業者などに売却する
- 同時にその事業者と、自宅についての賃貸借契約(家賃の支払い)を結ぶ
- 売却代金を一括で受け取りつつ、自宅には賃貸として住み続ける
つまり、「所有者」から「賃借人」に立場を変えながら、同じ家に住み続けるためのしくみです。リースバックを検討する人向けに、国土交通省は「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表し、基本的なスキームや注意点を整理しています。参考:国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」
1-2.誰が利用している?
国民生活センターの資料によると、住宅リースバック契約に関する相談の契約当事者の約7割が70歳以上というデータもあります。高齢期の「老後資金の確保」「住宅ローン返済」「介護・医療費の準備」などをきっかけに検討されるケースが多いようです。参考:国民生活センター「自宅を売っても住み続けられる? リースバックは慎重に検討し…」
2.老後にハウスリースバックが選ばれる主な理由(メリット)
2-1.まとまった現金を一括で得られる
- 自宅を売却するため、売却代金を一括で受け取れる
- 老後資金の不足分を補ったり、住宅ローン・借金の返済に充てたりできる
- お金の使い道に制限がない商品も多く、資金用途の自由度が高い
2-2.引っ越し不要で、住み慣れた環境を維持できる
- 売却後も同じ家に住み続けられるため、近所付き合いや通院先を変えなくてよい
- 高齢の親がいる場合、環境変化のストレスを減らせる
2-3.固定資産税や管理費などの負担が軽くなる場合も
- 所有権を手放すため、固定資産税やマンションの修繕積立金・管理費を支払わなくてよくなるケースが多い
- 家の維持管理や大規模修繕を自分で考えなくてよい安心感もある
こうした特徴から、「住み替えはしたくないが、お金は必要」というシニア世代にとって、魅力的に見える制度です。
3.見落としがちなデメリット・リスク
3-1.「ずっと住める」とは限らない
- 賃貸借契約の種類(普通借家契約・定期借家契約など)によっては、契約期間満了で退去が必要な場合もある
- 事業者が物件を第三者に売却するケースもあり、契約内容によっては住み続けられない可能性がある
国民生活センターは、「『ずっと住める』と誤解したまま契約してトラブルになる例がある」と注意喚起しています。参考:国民生活センター「自宅を売っても住み続けられる? リースバックは慎重に検討し…」
3-2.家賃が相場より高くなることがある
- 売却価格と家賃は事業者が自由に設定できるため、近隣の相場と比べて高い家賃になることがある
- 老後の収入(年金など)が今後減る可能性も踏まえると、長期的に支払い続けられるかの検討が必須
国民生活センターの資料でも、家賃値上げにより支払いが困難になった相談事例が紹介されています。
3-3.売却価格が「思ったより安い」ケースも
- リースバックは「そのまま住み続けられる」などのメリットがある分、通常の売却より価格が低くなる傾向があります
- 他の不動産会社による査定と比較せずに契約すると、相場よりかなり安い価格で売ってしまうリスクがある
3-4.高齢者を狙った強引な勧誘も
- 長時間の勧誘や、判断能力が低下した高齢者に不利な契約をさせる事例が問題になっています
- 「今すぐ契約しないと損をする」「ローン返済が苦しいならリースバック一択」といったセールストークには要注意
「老後の生活の安全」のための契約が、逆に生活を不安定にしてしまう事例もあるため、慎重な判断が必要です。
4.リバースモーゲージ・通常売却との違い
4-1.リースバックとリバースモーゲージの違い(ざっくり)
自宅を活用して資金を得る代表的な方法として、リバースモーゲージがあります。住宅金融支援機構は、リバースモーゲージや同機構の商品「リ・バース60」と、リースバックとの違いを次のように整理しています。参考:住宅金融支援機構「リ・バース60 Q&A」
- リースバック:自宅を売却し、買主と賃貸契約を結んで家賃を支払う(所有権は失う)
- リバースモーゲージ:自宅を担保に金融機関からお金を借り、契約者の死亡時などに売却して返済する(所有権は維持)
どちらも「自宅を活用して資金を得る」点は共通ですが、所有権を残すかどうか・毎月払うのが家賃か利息かといった違いがあり、向き・不向きが分かれます。
4-2.通常の売却との違い
- 通常の売却:売却後は引き渡しのため、基本的にその家から引っ越す必要がある
- リースバック:売却後も、一定期間同じ家に住み続けられる(ただし「ずっと」とは限らない)
国土交通省のガイドブックでも、「リースバック以外にも、通常の売却やリバースモーゲージなど複数の選択肢を比較すること」が大切だとされています。
5.相続・税金・契約に関する5つのよくある疑問
5-1.ハウスリースバックは相続対策になる?(条件次第で「メリット」にも「デメリット」にも)
リースバックは、「相続トラブルの予防」や「納税資金の確保」という意味では、相続対策の一つになり得ます。
- 自宅を売却して現金に変えることで、複数の相続人に分けやすくなる(遺産分割トラブルの予防=メリット)
- 相続税の納税資金として、売却代金の一部を確保しておける(納税資金対策=メリット)
一方で、
- 通常売却よりも売却価格が低くなりやすいため、資産全体としては「金銭的に損」になる可能性がある(デメリット)
- 「相続税そのものを大きく減らす」ような仕組みではなく、主に現金化・納税資金準備・分けやすさの対策にとどまる
つまり、「争族(あらそい)」を減らしたい人にとってはメリットになり得ますが、「相続税を劇的に減らしたい」人には向かない場合もあるというイメージです。
5-2.売った際の所得税(譲渡所得税)はどうなる?(利益が出れば「デメリット」、特例が使えれば中立〜軽減)
ハウスリースバックで自宅を売った場合も、税金の扱いは基本的に「自宅を売却したときの譲渡所得税」と同じです。
- 売却価格 ≧(購入価格+購入時・売却時の費用)なら譲渡所得がプラスになり、原則として所得税・住民税の対象(デメリット)
- 逆に、譲渡所得がマイナス、またはほとんど出ない場合は税額がゼロになることも多い
自宅(マイホーム)の場合、条件を満たせば「3,000万円特別控除」などの特例も使えます。参考:国税庁タックスアンサー
譲渡益が大きい人にとっては、譲渡所得税は「デメリット寄り」。一方、特例を活用して税額がほぼゼロなら、中立に近い扱いと考えられます。どの特例が使えるかは、所有期間や住んでいた期間など条件で変わるため、具体的な判断は税理士など専門家に相談するのが安心です。
5-3.契約者を変えて子どもが住むことはできる?(原則は「そのままでは難しい」=デメリット寄り)
リースバックの賃貸借契約は、通常の賃貸と同じく「契約者(借主)」が決まっており、無断で名義変更したり、子どもに住まわせたりすることは原則できません。
- 多くの契約では、賃借人の名義変更・転貸は事業者の承諾が必要
- 子どもがその家に住みたい場合は、事業者と新たに契約し直す・親族間売買+リースバックのスキームを組むなど、別の手続きが必要になることが多い
最近は、「親族間リースバック」「親子間売買+リースバック」のような形で、子どもが親の家を買い取って貸すスキームも紹介されていますが、一般のリースバックとは条件が異なります。参考:
「将来は子どもが住む前提」の場合、通常のリースバック契約だけに頼るのはデメリットが大きく、別のスキームも含めて専門家と設計する必要があると考えたほうが安全です。
5-4.何年住まないといけない?(「必ず○年」というルールはなく、条件次第で柔軟=メリット)
「リースバックしたら何年は必ず住まないといけない」という法律上の一律ルールはありません。実際に何年住めるか・最低どれくらい住む前提かは、契約書に書かれた内容次第です。
- 普通借家契約:2年などの契約期間で、更新料を払って更新していくケースが多い
- 定期借家契約:契約期間満了時に原則終了となり、更新は「新たな契約」として扱われる
また、多くのリースバックでは、借主(住んでいる側)からの中途解約条項が設けられ、事情が変われば途中で退去できるようにしている事例もあります。参考:
この点は、「状況に応じて住み続ける期間を自分で決めやすい」という意味でメリットですが、事業者やプランによって大きく異なるため、契約前に必ず確認しましょう。
5-5.途中で解約できる?(多くは「できる」が、条件次第で費用負担も=メリットとデメリット両面)
リースバックの賃貸借契約には、途中解約(中途解約)に関する条項が入っていることが多く、一定の予告期間をおいて借主から解約できるケースが一般的です。
- 「1〜3か月前までに書面で通知」などの条件付きで、借主から中途解約が可能な場合が多い(柔軟さ=メリット)
- 中途解約時に、違約金・原状回復費用・退去費用などの負担が発生することもあり、短期間で解約するとコスト面でデメリットになることも
中途解約条項がない場合でも、貸主・借主の合意による解除(合意解約)で退去できるケースがありますが、その場合も条件や費用は個別交渉となります。参考:
まとめると、「柔軟に解約できる」点はメリットですが、「いつでもノーコストで出られる」と考えると危険で、契約書の中途解約条項をよく確認しておく必要があります。
6.老後の家計とハウスリースバック|考えるべき5つのポイント
6-1.「家賃を一生払い続けられるか」を数字で見る
- 年金額・その他収入・将来の医療・介護費を考慮し、家賃を一生払い続けられるか試算する
- 物価高・医療費増加も踏まえ、家賃が上がる可能性もチェック
6-2.契約期間・契約種類(普通借家/定期借家)の確認
- 「契約更新はあるのか」「定期借家の場合、満了後どうなるのか」を必ず確認
- 「ずっと住める」と口頭で言われても、契約書に書かれていなければ効力は限定的
6-3.売却価格・家賃が相場と比べて妥当か
- 複数の不動産会社に査定を依頼し、売却価格の相場感をつかむ
- 近隣の家賃相場と比べて、家賃が極端に高くないかをチェック
6-4.家族と情報共有できているか
- 相続や今後の同居・介護を考えると、子ども世代と情報共有しておくことが大切
- 判断能力が落ちてから契約するのではなく、元気なうちに家族で話し合う
6-5.公的な相談窓口も活用する
- 国民生活センターやお住まいの消費生活センター
- 自治体の無料法律相談・ファイナンシャルプランナー相談
- 一般社団法人 住宅ローン問題解決支援機構「リースバックの相談先は?」
7.トラブル事例から学ぶ「契約前のチェックリスト」
国民生活センターの資料などから見える、よくあるトラブルのパターンをチェックリストにまとめます。
- □ 勧誘が長時間にわたり、断りづらい雰囲気だった
- □ 「ずっと住める」「生涯安心」と言われたが、契約書にその文言がない
- □ 売却価格が妥当か、他社の査定と比較していない
- □ 家賃や更新条件、退去が必要になるケースの説明があいまいだった
- □ 借金返済や生活費の補填のために、とりあえず契約しようとしている
- □ 判断能力が落ちている家族が、一人で契約しようとしている
上のチェック項目に複数当てはまる場合は、一度立ち止まって、第三者(家族・専門家・公的機関)に相談するほうが安全です。
8.老後の「住まいとお金」の一つの選択肢として
ハウスリースバックは、
- 住み慣れた家から離れたくない
- まとまった資金が必要になった
- 固定資産税や修繕の負担を軽くしたい
といったニーズに応える便利な選択肢のひとつです。一方で、
- 家賃負担が長期的に重くなる可能性
- 契約内容によっては、想定より早く退去が必要になるリスク
- 悪質な事業者との契約により、家もお金も失う危険
といった老後の生活を揺るがすリスクもはらんでいます。
大切なのは、ハウスリースバックだけを特別視するのではなく、
- 通常の売却+住み替え
- リバースモーゲージや「リ・バース60」などのローン商品
- 持ち家を売却して賃貸に移るシンプルな方法
- 高級マンションへの住み替えなど、他の老後の住まいの選択肢
と横並びで比較し、自分と家族の価値観・家計・健康状態に合うかどうかを考えることです。
同サイトでは、老後の住まいの別の選択肢として、「老後、高級マンションに住む」という選択肢も紹介しています。あわせて読むと、老後の住まいのイメージがより立体的になります。
ハウスリースバックは、正しく理解して使えば役に立つツールですが、家族や専門家と相談しながら慎重に進めるべき制度です。この記事が、「自分に合うかどうかを見きわめるための第一歩」になればうれしいです。
この記事のポイント
- ハウスリースバックは「売却+賃貸」をセットにした仕組みで、老後資金と住まいの両方に関わる制度
- メリットだけでなく、「ずっと住めるとは限らない」「家賃が相場より高い」「売却価格が低くなりやすい」などのリスクも大きい
- 相続対策・譲渡所得税・契約者変更・居住年数・中途解約などを事前に確認し、リバースモーゲージや通常売却と比較しながら検討することが大切
参考資料・リンク
- 国民生活センター「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!」
- 国民生活センター「自宅を売っても住み続けられる? リースバックは慎重に検討し…」
- 国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」
- 住宅金融支援機構「リ・バース60 Q&A」
- 国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」
- 国税庁 No.3223「譲渡所得の特別控除の種類」
- 山村忠夫法律事務所「リースバックとは?相続対策や遺産分割の問題解決に役立つ…」
- AGSリースバック「リースバックで相続対策をするメリット」
- 西日本不動産流通機構「親族間売買でリースバックは活用できるのか?」
- 一般社団法人 住宅ローン問題解決支援機構「リースバックの相談先は?」
免責事項
本記事は、公的機関等の情報をもとに執筆した一般的な解説であり、特定の商品・事業者を推奨するものではありません。また、お読みの方それぞれの状況に応じた個別のアドバイスではありません。具体的な契約・税金・相続・資金計画については、必ず金融機関・不動産会社・税理士・ファイナンシャルプランナー・弁護士等や、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
更新履歴
- 初版公開:2025年11月23日