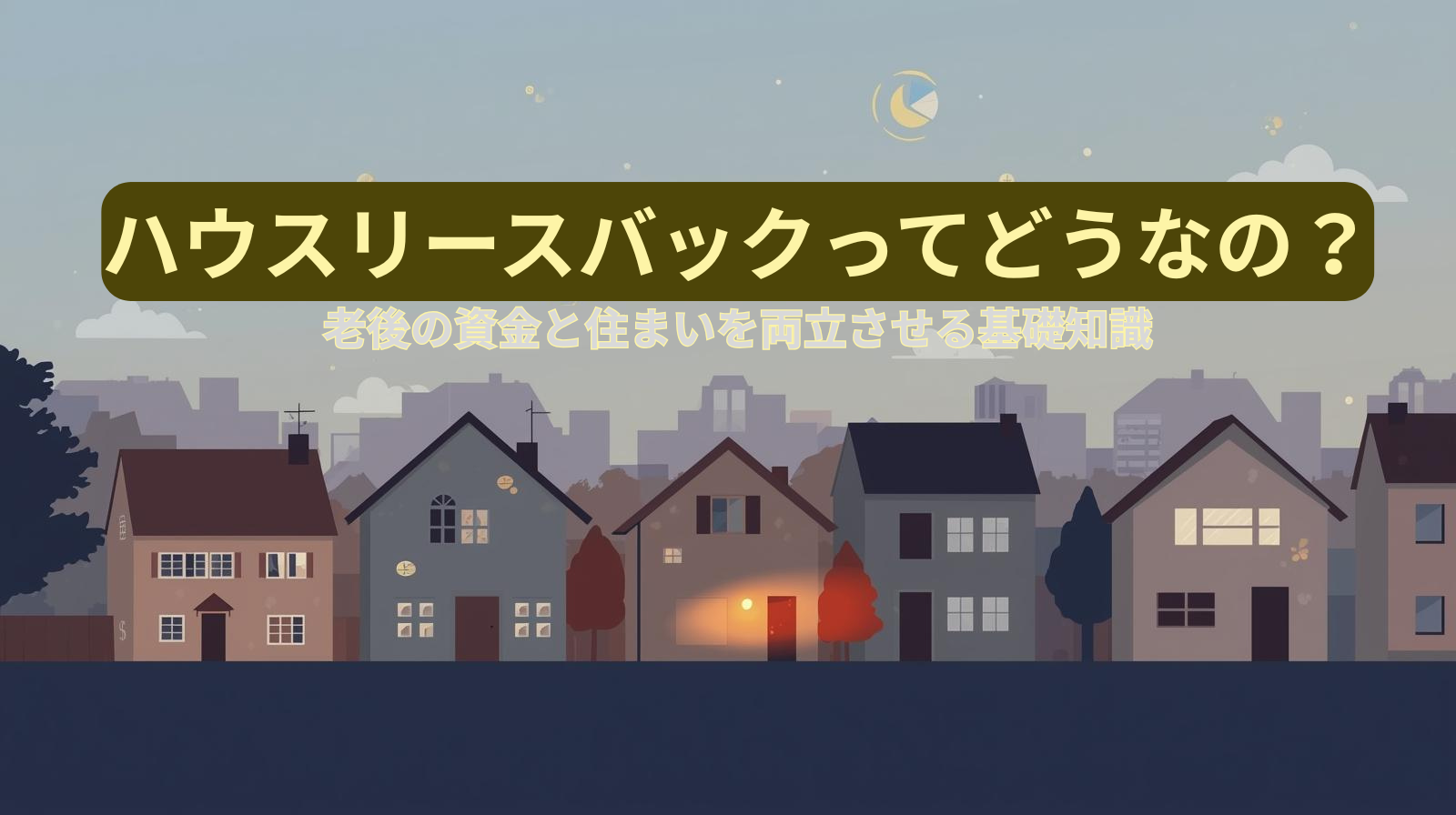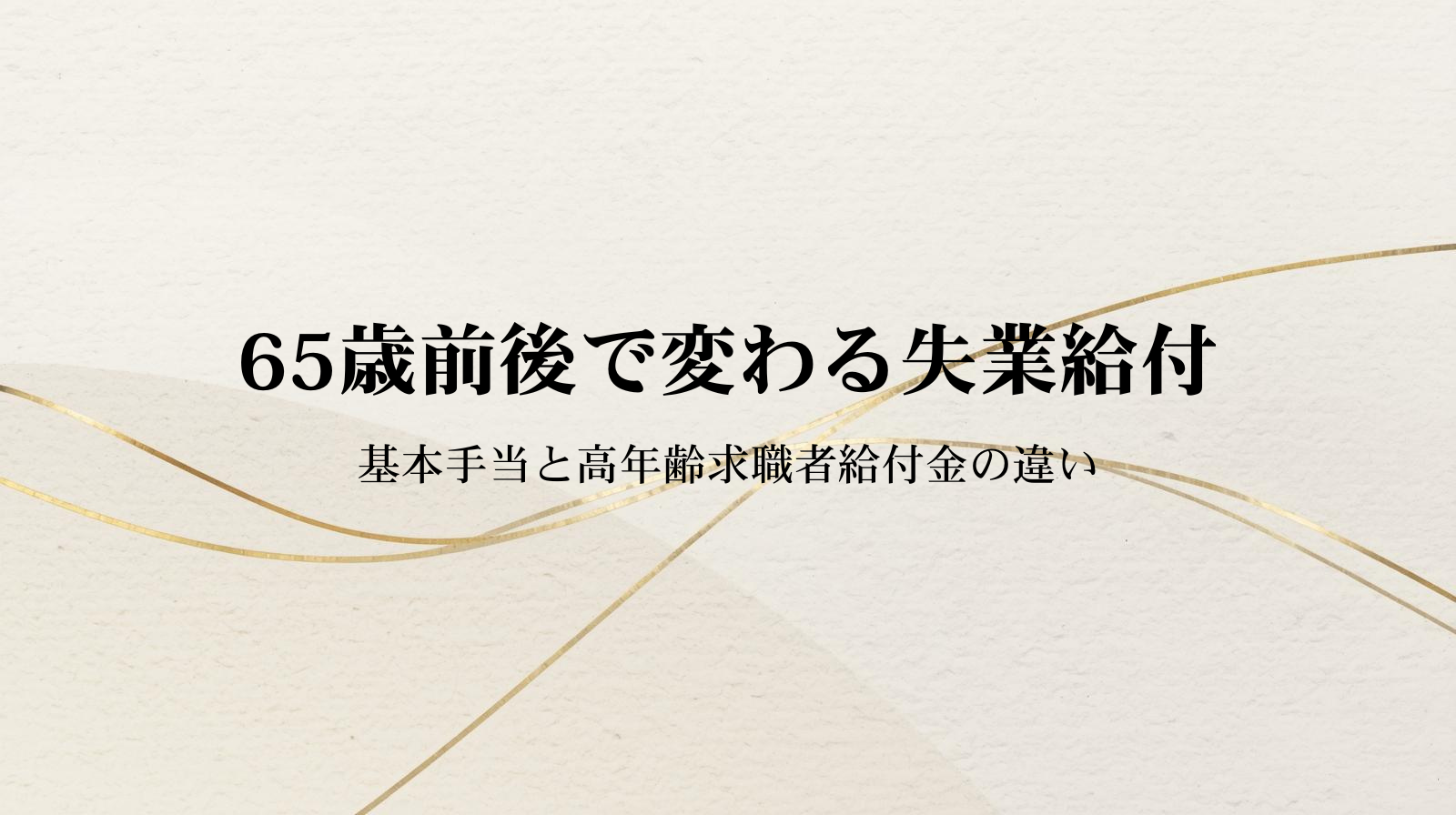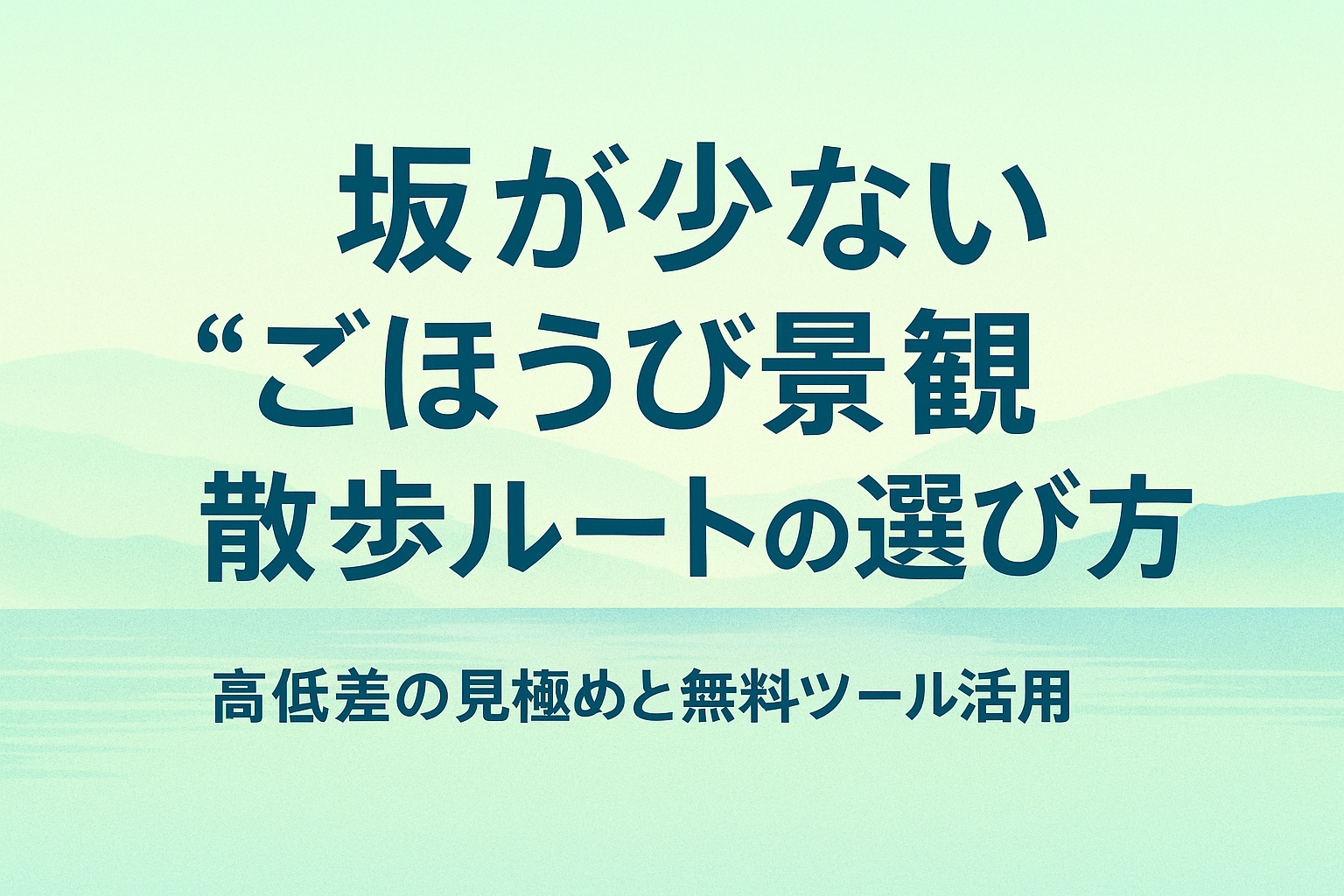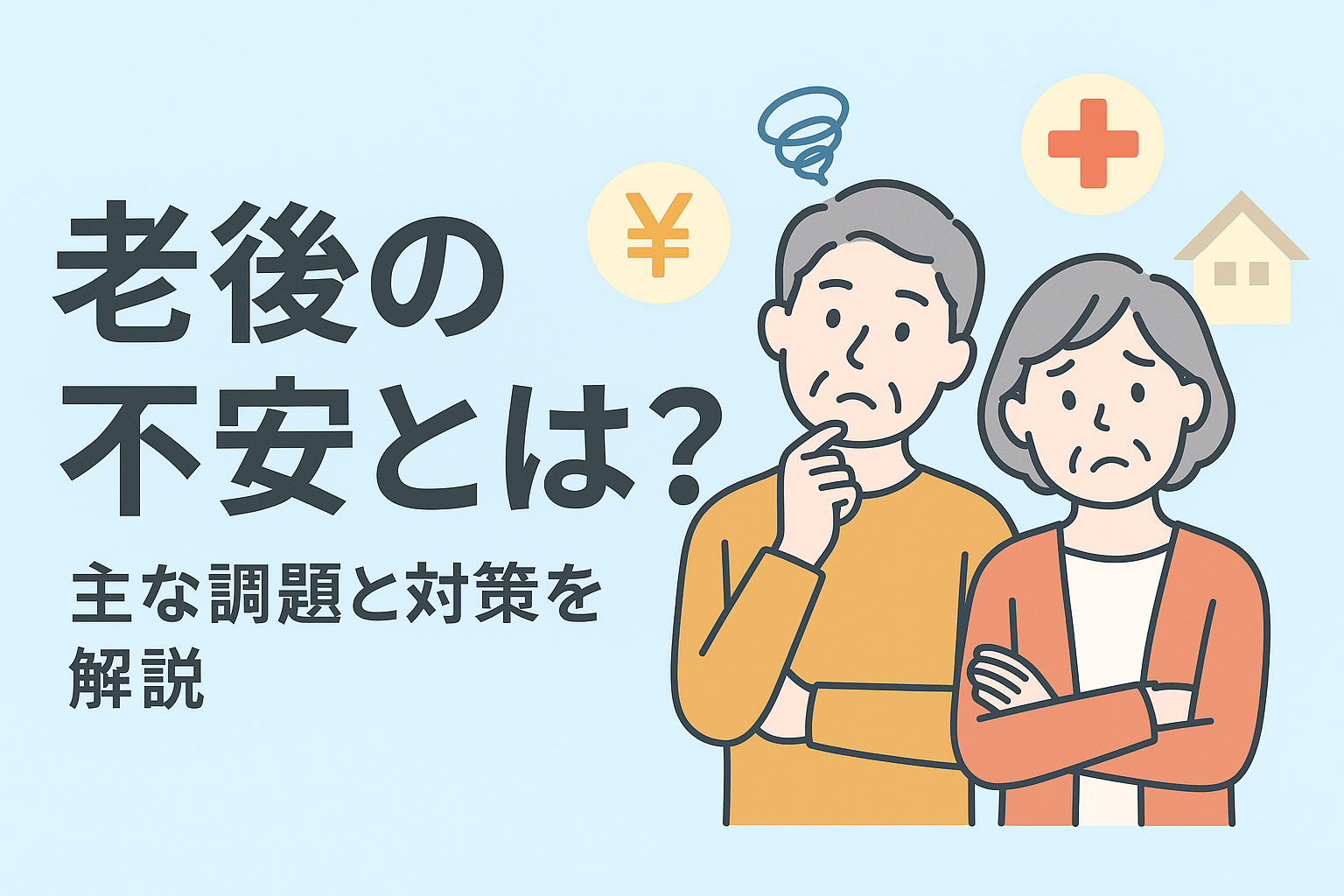「値段と量」で見る健康食品|1か月いくらまでならムリなく続けられる?
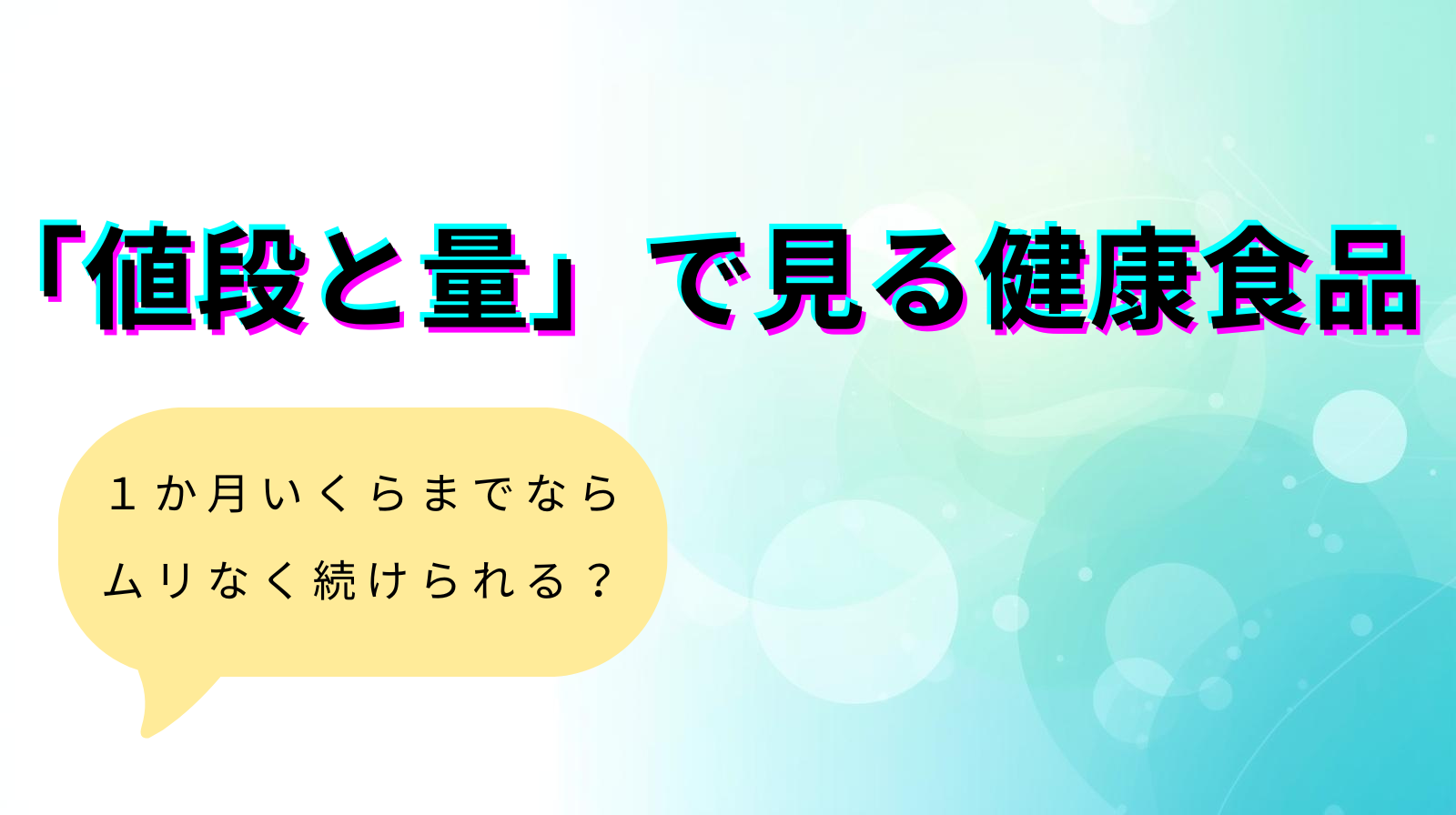
健康食品やサプリは、「体のために何かしておきたい」という気持ちを形にしやすいアイテムです。一方で、毎月の出費がじわじわ増えやすいという側面もあります。
民間調査では、健康食品を利用している人は年代が高くなるほど支出が増える傾向があり、60代以上では1か月あたり男性3,000円台前半、女性は4,000円前後という結果も出ています。さらに、健康食品に積極的なシニア層では、月1万円前後を投じるグループも確認されています。
この記事では、「どれが効くか」よりも「いくらなら続けられるか」という視点で、健康食品と家計のバランスを考えていきます。
この記事で得られること
- シニア世代の健康食品の平均的な支出イメージがつかめる
- 自分の家計に合わせた「1か月の健康食品予算」の決め方が分かる
- 値段と量をチェックする際の具体的なポイントが整理できる
- 定期購入や広告の「お得」に振り回されないための注意点が分かる
老後の暮らしにどう関わる?
- 健康食品は、うまく使えば「安心感」や「体調管理の補助」になります。
- しかし、年金中心の暮らしで毎月1万円以上かけ続けるとなると、旅行・趣味・交際費などを削る原因にもなりかねません。
- また、複数のサプリを重ねると「気づいたら毎月かなりの金額」になりやすく、定期購入トラブルが起きると解約にも手間がかかります。
だからこそ、老後の家計では「健康食品にかける上限」を早めに決めておくことが、安心につながります。
1.みんなは1か月いくらぐらい健康食品に使っている?
まずは「世の中の平均」をざっくり眺めてみます。
- 健康食品に関する消費者アンケートでは、健康食品を摂取している人のうち、60代以上の1か月あたり支出額は、男性が3,000円台前半、女性は4,000円前後と報告されています。
- 同じ調査で、摂取している健康食品の種類は年代を問わず2〜3種類が平均的で、年齢が上がるほど支出額が増える傾向があるとされています。
- 別のシニア向け調査では、健康食品に積極的な「健康投資型」の層では、月平均支出額が1万円を超えるグループも確認されています。
このあたりの数字から、「シニアの健康食品支出」は月3,000〜4,000円が一つの目安、かなり積極的な層では1万円前後というイメージが見えてきます。
もちろん、これはあくまで統計上の平均値であり、ここから外れているから良い・悪いという話ではありません。ただ、自分の支出を見直す“物差し”として知っておくと便利です。
2.「1か月いくらまで?」を考える3ステップ
では、自分の家計では「どのくらいまでなら無理なく続けられるか」をどう決めればよいでしょうか。ここでは、シンプルに3ステップで考えてみます。
ステップ1:健康食品の「現在地」を把握する
- 今飲んでいる健康食品をすべて書き出す(商品名でなくても「関節サポート」「マルチビタミン」などでOK)
- それぞれの1か月あたりの費用を計算する(例:1袋30日分3,000円 → 月3,000円)
- 合計して、今いくら使っているかを確認する
この時点で「え、こんなに?」となる方も少なくありません。
ステップ2:「生活費に対して何%か」で考える
たとえば、1か月の手取り(年金+パート収入など)が20万円だとします。
- 健康食品に3,000〜4,000円 → 生活費の約1.5〜2%
- 健康食品に1万円 → 生活費の約5%
生活費の2%前後(1日100〜150円=月3,000〜4,500円)であれば、「平均的な支出」とほぼ同じゾーンです。
一方で、5%(月1万円前後)を超える場合は、
- 旅行や趣味に回したいお金が削られていないか
- 同じ目的のサプリが重なっていないか
- 「なんとなく惰性で続けているだけ」のものが混ざっていないか
を一度見直してみる価値があります。
これはあくまで筆者の家計管理の目安であり、「必ずこのパーセンテージにしなければならない」という意味ではありません。ただ、数字で可視化することで、優先順位がつけやすくなるのは確かです。
ステップ3:上限額を「言葉」にして決める
- 「健康食品は月◯円まで」
- 「新しいサプリを足すときは、何か一つはやめる」
- 「定期購入は合計◯円までにする」
こうしたルールを、家計簿やメモ帳に書いておくだけでも、広告やセールに揺れにくくなります。
3.「値段と量」を見るときのチェックポイント
具体的な商品を選ぶときは、次のようなポイントを確認してみてください。
① 1日あたり・1か月あたりの実質コスト
- 「1袋◯円」ではなく、「1日あたりいくらか」に直して考える
- 「お試し価格」「初回◯%オフ」だけでなく、2回目以降の価格まで確認する
- 定期購入の場合は、最低何回続くといくらになるかを必ず計算する
② 1日何粒?何回?
- 1日6粒を2〜3回に分けて飲むより、1日1〜2回で済むものの方が続きやすいことが多い
- 飲み忘れが多いと、結果的に「高いのに効果も分からない」状態になりがち
③ 容量と「余り」の有無
- 30日分・60日分など、自分のペースに合う容量かを確認
- 大容量で安く見えても、飲みきれずに余らせるとかえって割高になる
4.定期購入の「本当の総額」を忘れない
ネット通販では、「初回◯円」「◯%オフ」「いつでも解約OK」といった健康食品の広告が多く見られます。
- 消費生活センターや消費者庁などは、健康食品の定期購入トラブルについて、たびたび注意喚起を行っています。
- 「お試し」のつもりで申し込んだら、実は複数回の購入が条件だった、解約の電話がつながらない、解約には追加料金が必要だった…といった事例も報告されています。
申し込む前に、次の点を必ずチェックしましょう。
- 定期購入かどうか(「単品購入」と選べるか)
- 最低○回継続などの条件がないか
- 初回価格だけでなく、2回目以降の価格と送料
- 解約方法(電話のみ/WEB可など)と、解約の締め切り日
「1回だけ試してみたい」場合は、・ドラッグストアで少量サイズを買う
・単品購入できる公式サイトを選ぶ
など、総額が読める買い方を選ぶと安心です。
5.老後の家計に効く「見直し」の考え方
① 同じ目的のものを整理する
- 関節サポート、骨の健康、カルシウム…など、実は目的が似ているサプリが重なっていないか
- 「同じ目的のものは最大2種類まで」など、上限を決めて整理する
② 「やめても平気だったもの」をチェック
- 一度、1〜2か月やめてみて、体調に大きな変化がなかったものは、候補のひとつ
- その分の予算を、運動・食事・趣味など、別の「健康・楽しみ」に回すのも選択肢です
③ 医師・薬剤師への相談をセットに
- 持病がある・複数の薬を飲んでいる場合は、必ず主治医や薬剤師に相談を
- 厚生労働省や消費者庁なども、「健康食品はあくまで補助であり、薬の代わりではない」と注意喚起しています。
6.まとめ|「月いくら?」より「納得して払えるか」
- シニア世代の健康食品支出は、調査では月3,000〜4,000円前後が一つの目安。
- 生活費に対して2%前後(1日100〜150円)なら、家計とのバランスが取りやすい人が多い一方、5%(月1万円前後)を超える場合は見直しを検討してもよいゾーン。
- 「値段と量」を見るときは、1日あたりコスト・飲む回数・容量・定期購入の総額をチェック。
- 老後の家計では、「健康食品にいくらまで出すか」を決めておくことで、健康と楽しみの両立がしやすくなります。
大事なのは、「なんとなく続けている」状態から一歩進んで、
「この金額なら、これだけの安心感が得られるから納得」と思えるラインを自分で決めること。
そのうえで、健康食品は生活習慣を支える“サポーター”として、無理のない距離感でつきあっていきたいですね。
更新履歴
- 初版公開:2025年11月19日
参考資料
- 矢野経済研究所「健康食品に関する消費者アンケート調査(2023年)」:
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3432 - 通販新聞オンライン「健康食品を摂取中の人は3割…購入先はショッピングサイトやドラッグストア」:
https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/72684 - 矢野経済研究所調査の解説記事「サプリメントや機能性表示食品の摂取率は約3割。」:
https://netshop.impress.co.jp/node/13574 - 電通ダイレクト「シニア世代の健康食品市場における購買動向の調査分析レポートを公表」:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000017763.html - 国民生活センター「健康食品等の『定期購入』のトラブル」:
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210617_1.pdf - 国民生活センター「1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた健康食品」:
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2017_33.html - 政府広報オンライン「ネット通販での『定期購入トラブル』契約時に確認すべきポイントは?」:
https://www.gov-online.go.jp/article/202012/entry-9175.html - 消費者庁「【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品等の『定期購入』のトラブルにご注意!」:
https://www.kportal.caa.go.jp/flyer/000967/ - 厚生労働省「いわゆる『健康食品』のホームページ」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html - 消費者庁「健康食品(食品安全に関する情報ポータル)」:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_food/