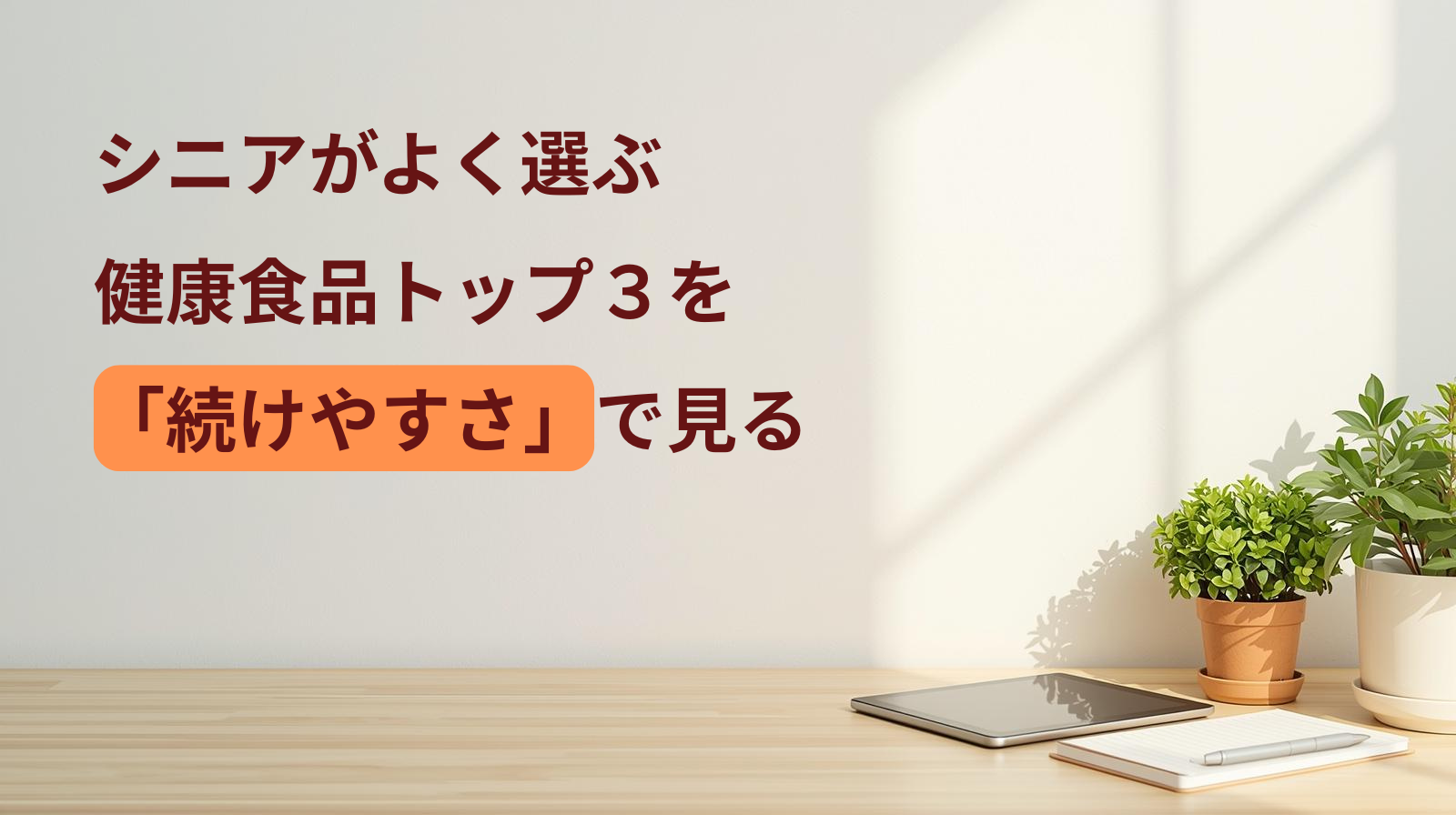年齢を重ねると、「元気に動きたい」「できるだけ自分のことは自分でしたい」という気持ちから、健康食品やサプリに目が向きやすくなります。
でも、どんなに評判が良くても、続かなければ意味がありません。
この記事では、シニア世代に選ばれがちな健康食品の「代表例」を3タイプ取り上げ、成分よりもまず“続けやすさ”の視点で整理します。
この記事で得られること
- シニアがよく選ぶ健康食品の「代表的な3タイプ」がざっくり分かる
- 粒の大きさ・飲む回数・価格など、続けやすさをチェックするポイントが整理できる
- 老後の家計と健康のバランスを崩さないための、「健康食品との付き合い方」のヒントが得られる
老後の暮らしにどう関わる?
- 健康食品は、うまく選べば「安心感」や「ちょっとした支え」になり得ます。
- 一方で、毎月の出費がふくらみすぎると、年金生活の家計を圧迫したり、他の楽しみ(旅行・趣味など)を削る原因にもなります。
- だからこそ、「効果がありそうか」だけでなく、続けやすさと家計への影響を一緒に見ることが、老後の安心につながります。
1.シニアが選びがちな健康食品「3つの代表例」
健康食品には無数の種類がありますが、シニア世代でよく見かけるのは次のようなタイプです(あくまで代表例です)。
- A:関節サポート系
例:グルコサミン・コンドロイチン・ヒアルロン酸などを含む錠剤やカプセル、コラーゲンペプチド入りのドリンク など
- B:ビタミン・ミネラルのベースサプリ
例:マルチビタミン錠剤、カルシウム+ビタミンDのサプリ、鉄や亜鉛など特定の栄養素を補う栄養機能食品 など
- C:腸内環境サポート系
例:乳酸菌・ビフィズス菌入りのヨーグルトや乳酸菌飲料、善玉菌を含むカプセル・顆粒タイプのサプリ など
内閣府などの調査でも、サプリ利用者の多くが2種類以上を併用しており、年齢が上がるほど併用数が増える傾向が報告されています。
参考:内閣府 消費者委員会「消費者の『健康食品』の利用に関する実態調査」
https://www.cao.go.jp/consumer/doc/201301_kenkoshokuhin_houkoku3.pdf
ここからは、「どれが一番良いか」ではなく、「自分にとって続けやすいか」に注目して見ていきます。
2.トップ3を「続けやすさ」で比べてみる
| タイプ | よくある目的 | 形状の傾向 | 続けやすさポイント | 注意したい点 |
|---|
| A:関節サポート系 | ひざ・腰の違和感ケアをサポートしたい | 錠剤・カプセル・顆粒が多い | 粒が大きくなりがちなので、飲み込みやすさを必ずチェック | 薬との飲み合わせ・長期利用については主治医や薬剤師に相談を |
| B:ビタミン・ミネラル系 | 食事の偏りをおぎないたい | 1日1〜数粒の錠剤が多い | 「1日◯回よりも1日1回」の方が、飲み忘れが少なく続きやすい | 他のサプリや栄養ドリンクと過剰摂取にならないように注意 |
| C:腸内環境サポート系 | おなかの調子を整えたい、便通をスムーズにしたい | カプセル・粉末・ヨーグルトタイプなどさまざま | 毎日の食習慣とセットにしやすい形(朝食ヨーグルト+サプリなど)だと習慣化しやすい | 糖質・脂質が多いお菓子タイプは、とり過ぎに要注意 |
同じ「関節サポート」「腸活」といった目的でも、粒の大きさ・飲む回数・味・価格は商品ごとにかなり違います。
成分だけでなく、「自分の生活リズムに無理なく組み込めるか?」を一緒に考えることが大切です。
3.続けやすさのチェックリスト(シニア目線)
① 飲みやすさ
- 粒が大きすぎないか、噛まなくても飲み込めるか
- ニオイ・味がつらくないか(匂いに敏感な人は特に)
- 1日何回飲むか。回数が少ないほど習慣にしやすいことが多い
② 生活リズムとの相性
- 「朝食後」「夕食後」など、既にある習慣とセットにできるか
- 外出が多い人は、持ち運びしやすい包装かどうか
- 飲み忘れ対策に、ピルケースやカレンダー等と組み合わせられるか
③ 家計とのバランス
- 1か月あたりの費用を計算し、「健康食品の予算」をあらかじめ決めておく
- 複数を併用するときは、トータルでいくらになるかを家計簿アプリなどで見える化
④ 定期購入・解約条件
4.「続けやすさ」と「安全性」を両立させるコツ
公的情報+かかりつけ医の意見をセットで
「足し算」よりも「引き算」も意識
- 気づくとサプリが3〜4種類…というケースは珍しくありません。
- 「同じような目的のものが重なっていないか?」「今、本当に必要なものはどれか?」を定期的に見直すことで、家計と健康の両方を守りやすくなります。
健康の“土台”を優先する
- 健康食品はあくまで補助役。歩く・食べる・眠るなどの生活習慣が「土台」です。
- サプリを足すより、一駅分多く歩く・野菜を一皿増やすなど、ゼロ円でできることも一緒に考えていきたいところです。
5.まとめ|「いいサプリ」より「続けられる距離感」
- シニア世代でよく選ばれる健康食品は、関節サポート系・ビタミンミネラル系・腸内環境サポート系など。
- どれを選ぶにしても、粒の大きさ・飲む回数・味・価格・契約条件など「続けやすさ」がとても大事。
- 公的情報と主治医のアドバイスを踏まえつつ、自分の生活リズムと家計に合うかどうかで選ぶと、老後の暮らしに無理なくフィットしやすくなります。
「どのサプリが一番効くか?」ではなく、「自分にとってちょうどいい付き合い方は何か?」という視点で、健康食品を選んでいきましょう。
更新履歴
ABOUT ME

はじめまして!
ニカドットを運営している**mondy(モンディー)**です。
広島県出身、34歳、牡牛座・O型。
現在は建設業に勤めながら、副業でこのブログを運営しています。
趣味は旅行、ゴルフ、サウナ(サ活)、漫画、野球観戦、散歩など。
「これからの人生をもっと楽しく!」をテーマに、笑顔になれる情報を発信中です。
みなさんと一緒に、前向きな未来を作っていけたらうれしいです。
応援よろしくお願いします!