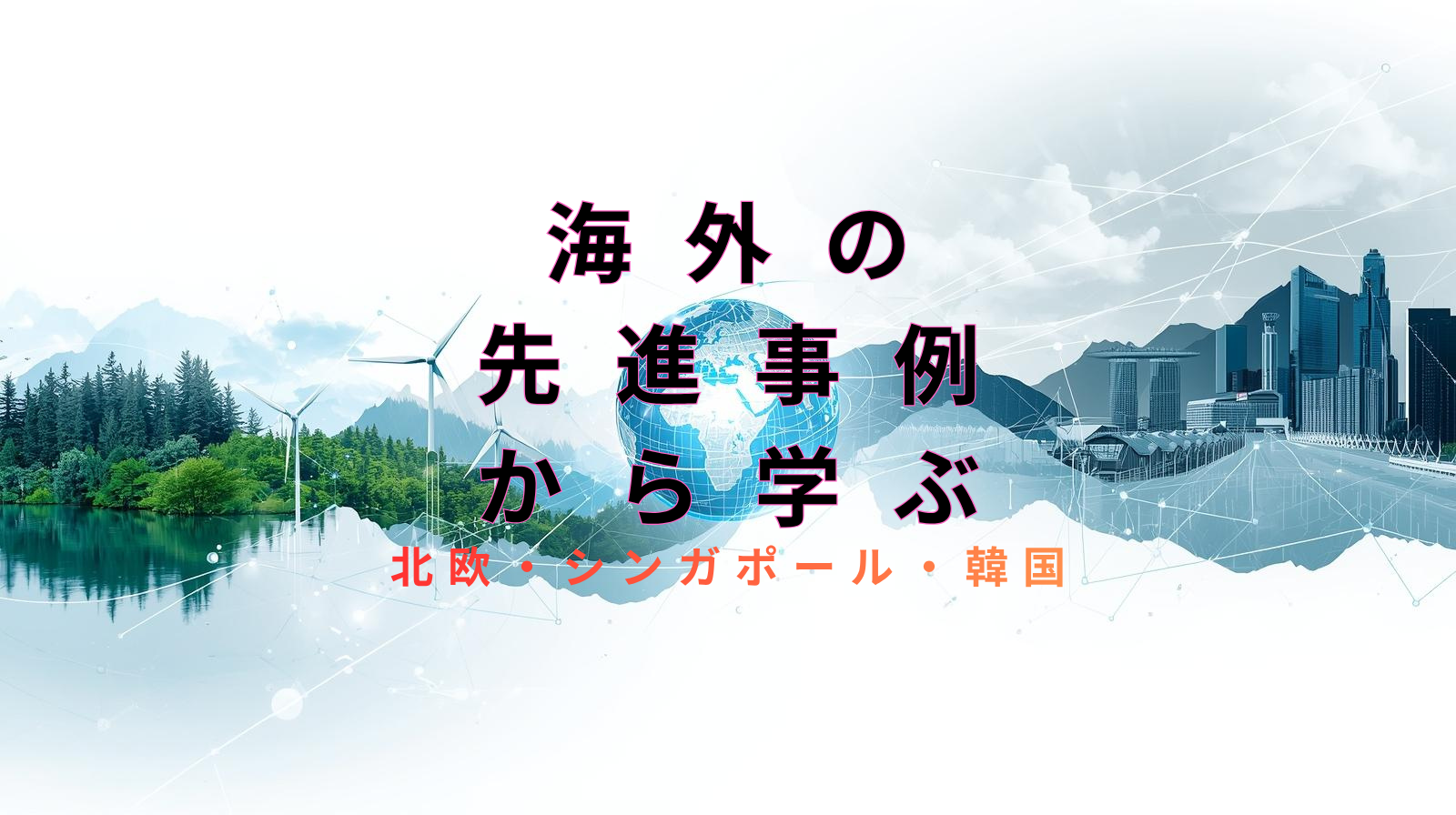旅とレジャーの未来|バリアフリー観光・オンデマンド交通・温泉DX

旅行はぜいたくじゃない。生きる楽しみのど真ん中です。
でも現実はこういう声もよく聞きます。
- 「階段が多い宿や温泉は正直しんどい」
- 「駅から目的地までが一番キツい」
- 「遠出は疲れるから、もう無理かなと思ってる」
いま、観光の世界でこの課題に本気で手がつき始めています。ポイントは3つ。
- ① 行きたい場所にちゃんと“行ける”ようにする(移動支援+観光)
- ② 泊まる場所・温泉そのものを「誰でも使いやすい形」にする(ユニバーサル設計)
- ③ 遠くじゃなくて“近場×短泊”をちゃんと提案する(ムリしない旅)
「年だからもう旅行はいい」じゃなくて、「年だからこそ旅行に行けるようにまちが変わる」という考え方へ。
これが、これからのレジャーの当たり前になっていきます。
① 移動支援と観光の融合|”ドア to 観光地”までセットで考える
これまでの観光は「現地に着いてからは自己責任」でした。
駅までは鉄道、そこから先はバスがなければタクシー、タクシーがなければ歩き…という世界観。でも、それは体力が落ちてきた人や、足・腰に不安がある人にはかなりハードルが高い。
そこで広がっているのが、オンデマンド交通や地域MaaS(予約して乗れる小型バスや地域の配車サービス)と観光をワンセットで考える動きです。これは「地域MaaS(マース)」とも呼ばれていて、簡単に言うと「必要なタイミングで呼べる、地域の移動インフラ」。
参考:AIオンデマンド交通の取組(国交省) / デマンド型交通の手引き(PDF)
イメージはこうです:
- スマホや電話で乗車時間を予約すると、小型のシャトルが自宅・宿・駅前まで迎えに来る
- 目的地は「観光地そのもの」や「温泉の入り口」までOK(“最寄りのバス停で降りたらそこから坂道20分”をなくす)
- 荷物や杖があっても遠慮しなくてよい前提で設計されている
つまり「旅行=まず移動をあきらめる」ではなく、移動こそが観光サービスの一部として扱われ始めているんです。
さらに、こういうオンデマンド交通は、地元の人の日常の足としても動くことが多いので、観光だけの“特別なもの”じゃないのもポイント。
観光と暮らしの移動が同じ仕組みで守られる=地域全体の安心が上がる、という考え方です。
② 宿・温泉のユニバーサル設計|「段差がありますので気をつけてください」からの卒業
最近の宿や温泉施設は、見た目の“和”や“風情”を残しつつ、安全に動けるつくりにゆっくり変わりつつあります。これをここでは「ユニバーサル設計」と呼びます。バリアフリー(段差をなくす、手すりをつける)だけじゃなく、その場所の使い方自体が“やさしい”方向に変わってきているイメージです。
関連:観光庁|ユニバーサルツーリズムの推進 / 心のバリアフリー認定制度
たとえば、こんな工夫があります:
- 浴槽の入り口が浅い・広い
脚を高く上げなくても入りやすい。足腰に不安があっても安心してゆっくり浸かれる。 - 手すりの位置が「ちゃんと持てる位置」
“形だけの手すり”ではなく、実際に体重を預けやすい高さと角度にしてある。 - 車いすや歩行器のまま移動しやすい動線
廊下の幅、エレベーターの広さ、部屋の入口の段差など、移動そのものがストレスにならない。 - 食事処の椅子・テーブルが選べる
低い座卓だけじゃなく、イス+テーブル席もある。長時間座っても腰がラク。
大事なのは、「特別な介護施設っぽい見た目」にしないこと。
旅行は“気持ちが休まる時間”だから、デザインと安心を両立させる=温泉DX/宿DX という発想になっています。関連:観光庁|観光DXの推進
この流れは、段差や手すりといった“ハード”の話だけじゃなく、スタッフ側の体制にも広がっています。
- チェックイン時に「お手伝いが必要なことありますか?」と最初から聞いてくれる
- 入浴や移動のサポートを断りなく触らず、声かけのうえで行う
- 食物アレルギーや薬との関係で食事の相談に乗れる
つまり「不便なら言ってください」から、「はじめからあなたに合わせます」へ。
これが“ユニバーサル(誰にとっても使いやすい)”な旅の考え方です。
③ “近場×短泊”のすすめ|遠くに行かなくても、人生はちゃんと満たせる
もうひとつ大きく変わりつつあるのが、旅のスタイルそのもの。
これから主流になっていくのは、「遠い観光地へ年1回ガツンと」より「近場に一泊または日帰りをくり返す」という形です。これはただの節約術ではなく、ものすごく合理的な健康戦略でもあります。
理由は3つ:
- 移動が短い=体力の消耗が少ない
“着いた瞬間もうクタクタ”にならない。 - 予定を詰め込まなくていい
「観光地を3つハシゴ」ではなく「1か所でゆっくりごはん・温泉・昼寝」。滞在型。 - 「また来れる場所」になる
“ここ好きだな”と感じた場所を、月1・季節ごとにリピートできる。これ、メンタルの支えとしてめちゃくちゃ大きい。
ポイントは“気づいたら毎月リセットできる場所がある”感覚をつくることなんです。
「行けるところ」があると、人はちゃんと外に出る理由を持ち続けられる。これは孤立を防ぐことにもつながります。
近場×短泊の提案は、観光側にとってもチャンスです。
大規模リゾートじゃなくても、
- バリアが少ない小さな温泉宿
- 地元食材のやさしいごはん
- オンデマンド交通で玄関まで送迎
こういう「ちゃんと安心して行ける休憩所」を地域ごとに持てれば、それはもう立派な観光資源。
これが“観光”と“暮らしのインフラ”の境目がなくなっていく未来のイメージです。
この記事のポイント
- 移動そのものが観光サービスになる
駅から先の「最後の1km問題」にオンデマンド交通で応える流れが広がる。 - 宿・温泉は「安心して楽しめる設計」にアップデート中
段差・手すりだけじゃなく、声かけ・食事・動線まで“使う人基準”に変わってきている。(ユニバーサルツーリズム) - これからの旅行は“近場×短泊”でいい
疲れすぎない・また行ける・生活リズムを壊さない。この形こそ「続けられるレジャー」。観光DXで予約・決済・混雑回避もラク。
旅行は若い人のものじゃない。
これからは「年齢に合わせて旅行側が変わってくれる時代」です。
参考・キーワード(後で公式URLに差し替えOK)
- 観光庁:バリアフリー観光・ユニバーサルツーリズム(公式情報)
- 国土交通省:地域MaaS / AIオンデマンド交通(地域の移動支援)
- 観光庁:観光DXの推進 / 観光DX説明資料(PDF)
更新履歴
- 初版公開:2025年10月30日
- 構成調整:近場×短泊の考え方を追記(2025年10月30日)