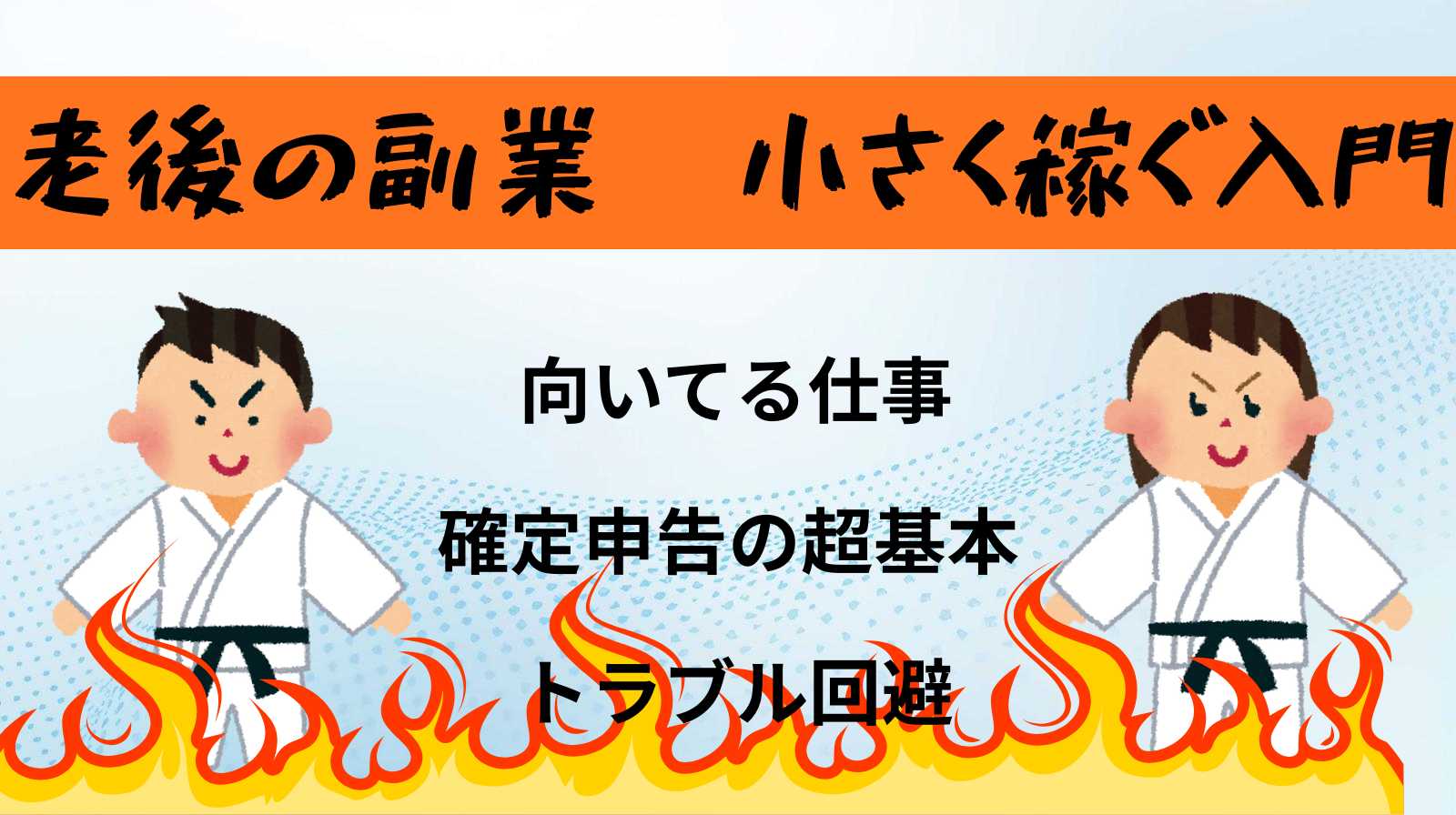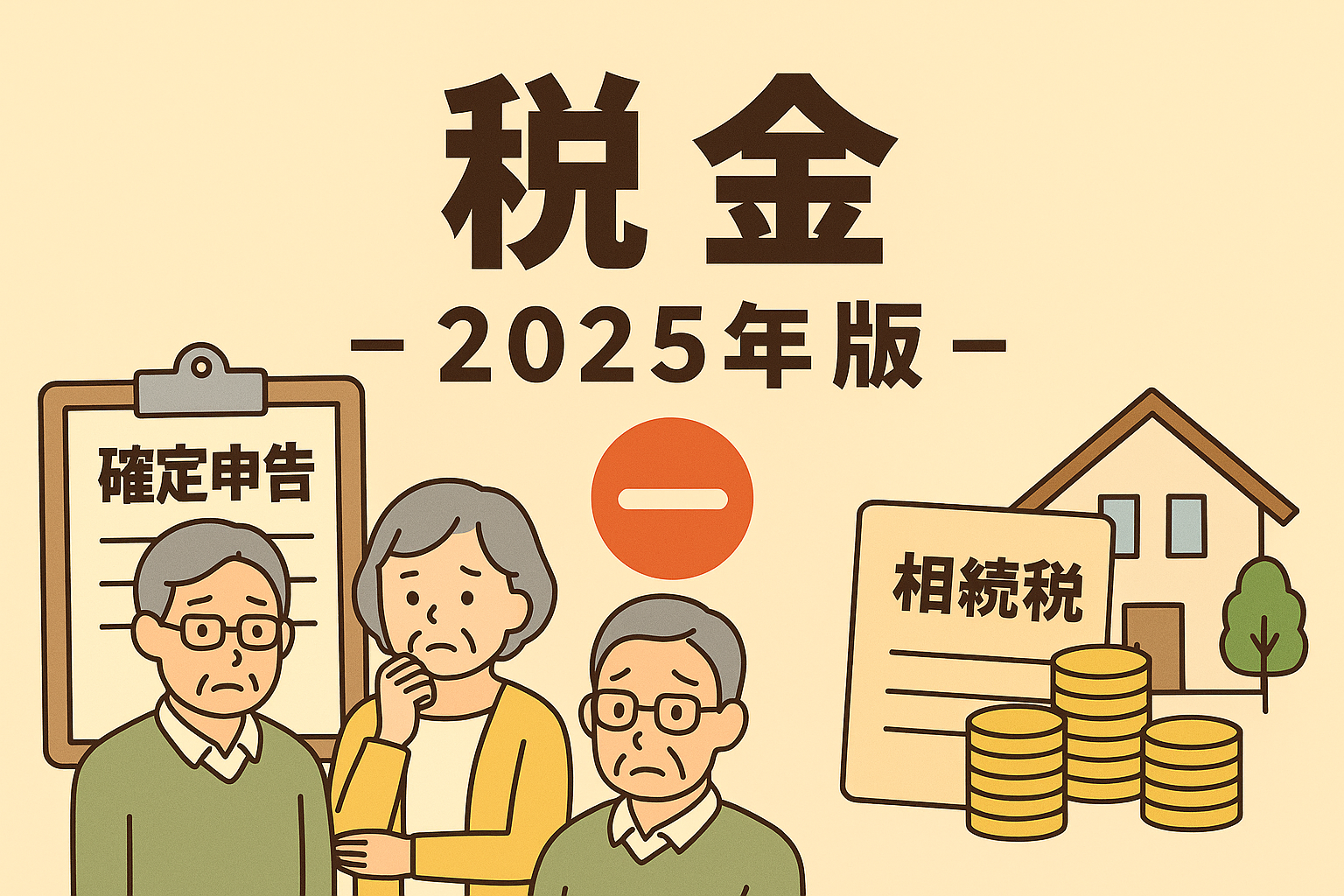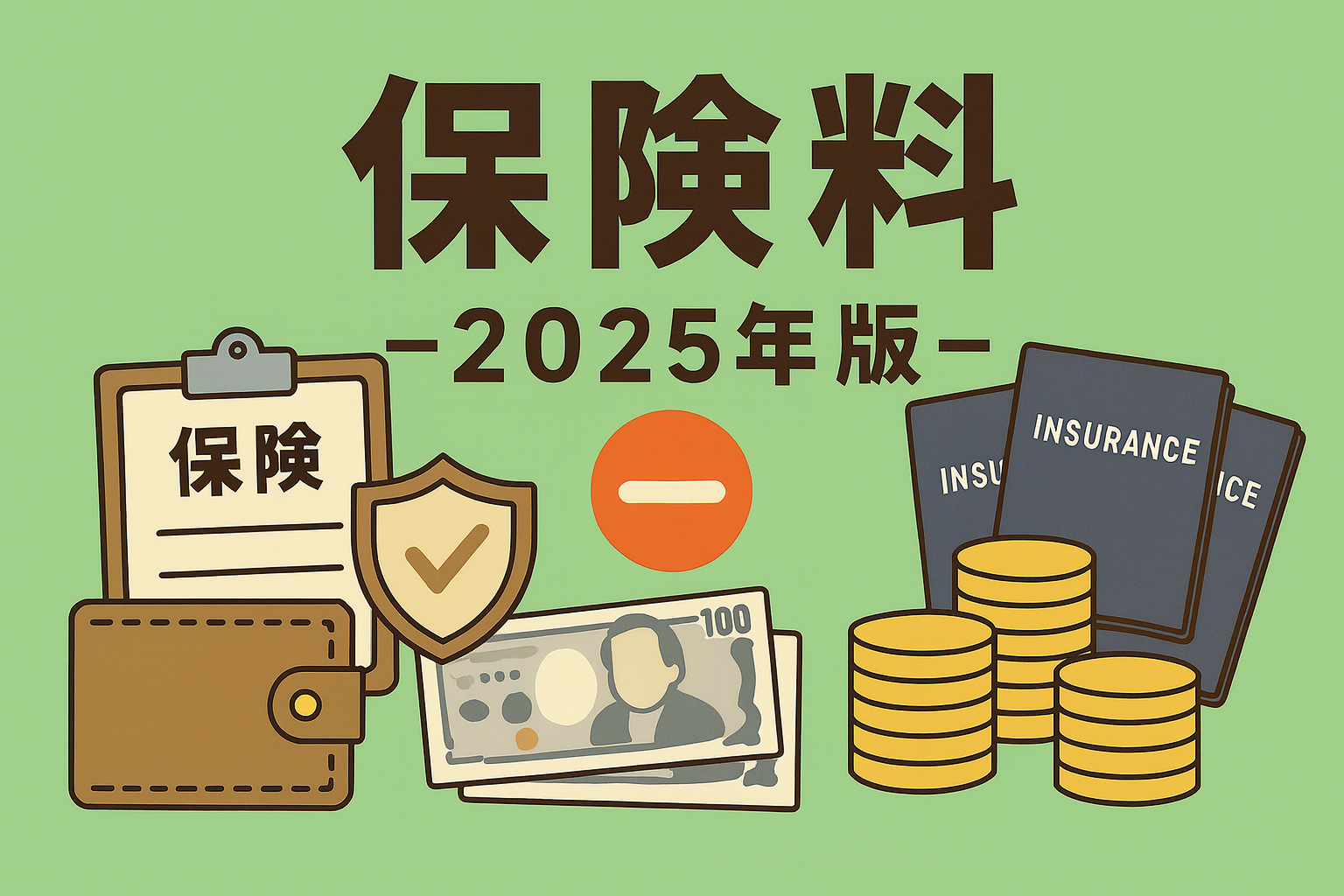老後、「高級マンションに住む」という選択肢|メリット・注意点・相続税の視点まで

「老後は駅近の高級マンションで、便利に安心して暮らしたい」──そんな声を耳にすることが増えました。
日本はすでに高齢化率29.1%(65歳以上が約3,623万人)の超高齢社会です。内閣府『令和6年版 高齢社会白書』でも、今後しばらくは高齢化が続くと示されています。
また、国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」では、マンションの世帯主は60代・70代の割合が大きく、シニアがマンションで暮らすケースが着実に増えている状況がわかります。マンションに関する統計・データ(国土交通省)
そのなかでも、設備やサービスが充実した「高級マンション」は、老後の住まいとして注目される選択肢のひとつです。一方で、購入価格や管理費、相続・税金のことなど、冷静に考えたいポイントもたくさんあります。
※本記事は、制度や統計の概要をもとにした一般的な情報です。特定の物件や投資をすすめるものではなく、最終判断は不動産会社・税理士・ファイナンシャルプランナー等の専門家とご相談ください。
この記事で得られること
- 日本の高齢化と「高級マンション需要」が生まれている背景が分かる
- 老後に高級マンションで暮らすメリットと注意点が整理できる
- サ高住や有料老人ホームなど他の住まいとの違いがイメージしやすくなる
- 「高級マンションは相続税対策になるの?」という疑問に、2024年以降のルールを踏まえて概要がつかめる
老後にどう関わるテーマ?
- 「どこに住むか」は、老後の安心・お金・健康・人間関係すべてに直結する
- 高級マンションは、利便性・安全性・快適さを一度に手に入れやすいが、そのぶんコスト・税金・介護との相性をよく考える必要がある
- この記事は、「憧れ」ではなく数字と制度を踏まえた現実的な選択肢として、高級マンションを比較するためのガイド
1.データで見る「シニア × マンション」と高級マンション需要
高齢化が進む日本と、マンションで暮らすシニアの増加
内閣府の高齢社会白書によると、2023年10月1日現在、日本の65歳以上人口は約3,623万人、高齢化率は29.1%。今後もしばらく高い水準が続く見通しです。
一方、国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」では、マンション世帯主の年齢構成を継続的に調査しています。詳細はPDF(データ編)に記載されていますが、
- 60代・70代の世帯主が占める割合が増加
- 「このまま永住したい」と考える人も依然として多い
など、「老後もマンションで暮らす」という流れが見て取れます。
シニア向け分譲マンションという市場
不動産データ会社・東京カンテイの調査(2022年)では、2023年までの供給予定を含めたシニア向け分譲マンションは全国で98物件・14,947戸とされています。全日不動産協会「シニア向け分譲マンションの供給動向から見える時代の変遷」
物件数自体はまだ多くありませんが、
- 都市部の駅近
- 温泉地・リゾート地
など、「老後の暮らし」にフォーカスしたマンションが、少しずつ増えてきています。
2.高級マンションが老後に選ばれる主なメリット
① 駅近・徒歩圏生活で、車がなくても動ける
- 駅・バス停・スーパー・病院・薬局が徒歩圏内にまとまっている物件が多い
- エレベーターでフラットに移動できるため、足腰が弱ってきても比較的動きやすい
- 悪天候でも外出のハードルが下がり、フレイル予防(外出機会の維持)にもつながる
② 防犯・防災・管理の安心感
- オートロック・防犯カメラ・宅配ボックスなど、設備面での安心感
- 管理員・コンシェルジュ常駐など、一人暮らしでも不安になりにくい環境
- 新しい物件ほど、耐震性能や非常用設備(非常用発電・備蓄倉庫など)に配慮されているケースも
③ 共用施設・サービスで「楽しみ」と「ゆるいつながり」を作りやすい
- ラウンジ・カフェスペース・フィットネス・シアタールームなどの共用施設
- 住民向けのサークル活動やイベントで、ご近所づきあいの入口が作りやすい
戸建てで「夫婦だけで閉じこもりがち」だった人にとって、ほどよい距離感のコミュニティを持てるのは大きなメリットです。
3.それでもチェックしたい「落とし穴」
① 管理費・修繕積立金など月々の固定費
- 高級マンションほど、共用施設・サービスが充実している=管理費が高くなりやすい
- 築年数が経つと、大規模修繕のために修繕積立金の値上げがおこなわれることも多い
- 「年金+金融資産の取り崩し」で暮らす期間が長いほど、月額数万円の差が大きく効いてくる
購入前に、
- 現在の管理費・修繕積立金・駐車場代など
- 将来の修繕計画と、そのときの積立金見込み
は必ずチェックしておきたいポイントです。
② 介護が必要になったとき、どこまで自宅で暮らせるか
- 一般の高級マンションは、「介護・看護込みの住まい」ではない
- 要介護度が上がると、訪問介護や家族のサポートに頼る部分が増える
- 「どの程度の状態まで自宅で暮らすのか」「その先はどこに移るのか」を家族で話し合っておく必要がある
③ 管理組合の運営・合意形成
- 修繕計画・防災対策・共用施設の維持など、住民同士の意見調整が必要
- シニア世帯が増えると、理事会や委員会の役割を担う人が不足しがち
- 購入前に、「総会議事録」や「長期修繕計画書」を見せてもらえると安心
④ 災害・停電時のリスク(特に高層階)
- エレベーター停止時に、高層階からの上下移動が困難になる
- 給水・トイレ・空調など、在宅避難が長期化した場合の備えが必要
4.高級マンションだけじゃない、シニア向け住まいの選択肢
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
バリアフリー構造の賃貸住宅に、安否確認や生活相談などのサービスが付いた住まいです。国土交通省のまとめでは、2025年10月末時点で8,332件・約29万戸が登録されています。サービス付き高齢者向け住宅の最新動向
- 持ち家ではなく賃貸なので、相続や売却の手間は少ない
- 介護が必要になった場合は、外部の介護サービスを組み合わせて使うスタイル
有料老人ホーム・CCRC型施設
- 「住まい+介護・医療・食事」をセットで提供する施設
- 入居一時金+月額費用は高めだが、介護体制が整っている安心感がほしい人向け
今の住まいをリフォーム+見守りサービス
- 手すり・段差解消・断熱・浴室リフォームなどで、今の家を「老後仕様」にする
- 見守りセンサー・オンライン診療・フードデリバリーなどを組み合わせて、できるだけ自宅で暮らす
高級マンションは、これらの選択肢の一つにすぎません。「何をいちばん大事にしたいか(立地/介護/お金/つながり)」を整理して比べることが大切です。
5.高級マンションは相続税の“節税対策”になるのか?
「現金で持つより、都心のタワーマンションにしておけば相続税が安くなる」──いわゆる『タワマン節税』と呼ばれてきた考え方があります。
これまで:評価額が「時価の4割程度」にとどまるケースも
国税庁の有識者会議資料などによると、マンションの相続税評価額と市場価格の乖離が問題になっていました。中には、相続税評価額が市場価格の4割程度にとどまるケースもあったとされています。国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」
2024年1月以降:評価額は「時価の6割程度」が下限に
こうした過度な節税を抑えるため、2024年1月1日以降の相続・贈与から、区分所有マンションの評価方法が見直しされました。
- 市場価格と相続税評価額の「乖離率」を算出
- 評価額が市場価格の6割未満にならないよう、補正をかける
- 築年数・総階数・所在階・敷地持分などを加味して区分所有補正率を計算
この結果、マンションの相続税評価額は、原則として「時価の6割程度」が最低ラインになる仕組みになりました。 参考:SUUMO「マンションの相続税評価額を見直し 市場価格の6割を最低ラインに」/朝日新聞デジタル「マンションの相続税はいくら?タワマン節税の行方」/ミネルバ税理士法人「マンション相続税評価改正」
それでも「現金より有利」なケースはあるが、専門家相談が必須
- 評価が6割程度になっても、現金(評価100%)より相続税が軽くなるケースはありうる
- 賃貸に出しているマンションは、「貸家・貸家建付地」としてさらに評価が下がる仕組みもある
- 一方で、購入時の借入・維持費・空室リスクなどを考えると、節税だけを目的にマンションを買うのは危険
相続税対策として高級マンションを検討する場合は、
- 家族の相続全体のバランス(誰に何をどのくらい残すか)
- 現金・保険・不動産の割合
- 将来の売却・住み替えのしやすさ
なども含めて、税理士やFPと一緒にシミュレーションすることが必須です。「とりあえずタワマンを買えば節税できる」という時代ではなくなっています。
※相続税・贈与税の具体的な計算は非常に複雑であり、本記事はあくまで概要の紹介です。詳細は必ず専門家へご相談ください。
6.まとめ|高級マンションは「ごほうび」ではなく「戦略」として考える
- 日本は高齢化率29.1%の超高齢社会で、シニアのマンション居住は増加している
- 高級マンションは、駅近・安全性・共用施設など老後と相性の良いメリットが多い
- 一方で、管理費・修繕積立金・介護との相性・災害時リスクなど、長期目線でのチェックポイントも多い
- 相続税対策としては、2024年以降は「時価の6割程度」が下限となり、過度なタワマン節税は難しくなっている
- サ高住・有料老人ホーム・自宅リフォームなど、他の選択肢と比べながら、自分と家族にとって一番ラクで安心な住まい方を探すことが大切
「老後だから高級マンションに住まなきゃいけない」わけでも、「高級マンションに住めたら勝ち」なわけでもありません。
お金・体力・家族・趣味・仕事とのバランスを見ながら、冷静に「住まいの戦略」を考えていきましょう。
参考リンク・出典(外部サイト)
- 内閣府『令和6年版 高齢社会白書』1-1-1 高齢化の現状と将来像
- 国土交通省「マンションに関する統計・データ等」(令和5年度マンション総合調査)
- (公社)全日本不動産協会「シニア向け分譲マンションの供給動向から見える時代の変遷」
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「サービス付き高齢者向け住宅の最新動向(2025年10月)」
- SUUMO「マンションの相続税評価額を見直し 市場価格の6割を最低ラインに」
- 朝日新聞デジタル「マンションの相続税はいくら? タワマン節税の行方」
- ミネルバ税理士法人「マンション相続税評価改正」