他国の年金

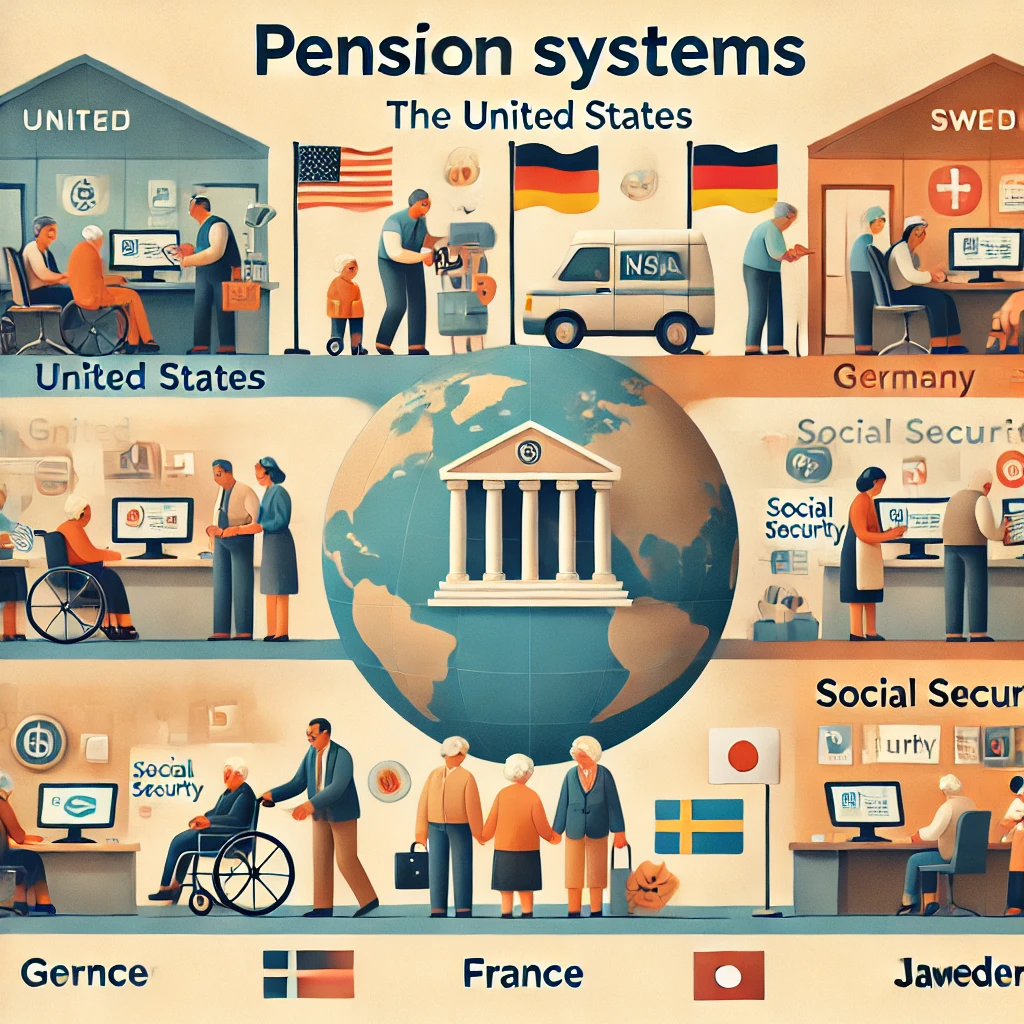
日本の歴史を調べたところで、今回は他国の年金制度について紹介していきます。
各国の年金制度は、その国の社会構造や経済状況に応じて多様な形式を持ち、特徴や課題も様々です。
その中で特徴・問題点についてまとめました。(2024年時点)
もっと詳しく一つの国をまとめると面白そうなので、また機会があれば紹介しようと思います。
1.主な国々の年金制度の特徴
日本
全ての国民が加入する「国民年金(基礎年金)」と、主に会社員や公務員が加入する「厚生年金」の二階建て構造になっている。
現役世代が納めた保険料を現在の年金受給者に充てる「賦課方式」を採用している。
支給開始年齢は基本65歳で、最低加入期間は約10年となっている。
アメリカ合衆国
公的年金として「社会保障(Social Security)」があり、被用者や自営業者が対象です。
受給開始年齢は66歳で、最低加入期間は40クレジット(約10年)とされています。
年金額は生涯の平均所得に基づき計算され、個人の所得に応じて給付額が変動します。
イギリス
公的年金は、一定以上の所得がある居住者が対象で、所得に応じて保険料が決まります。
給付額は定額で、低所得の高齢者を支援する「年金クレジット」も存在します。
公的年金が所得の再分配を担う制度として位置付けられています。
ドイツ
費用者や一部の自営業者が加入義務を持ち、受給開始年齢は65歳7ヶ月(2029年までに67歳へ引き上げ予定)です。
最低加入期間は5年とされています。
賦課方式を採用しており、現役世代が高齢者を支える仕組みです。
フランス
被用者や自営業者が加入義務を持ち、受給開始年齢は62歳(満額支給は67歳)です。
最低加入期間の定めはありません。
公的年金と一体運用されている私的年金分も計上されており、保険料率が高めに設定されています。
スウェーデン
個人の所得に基づく年金と最低の生活を保証する、保証年金の二本立てで構成されています。
受給開始年齢は62歳、保証年金は65歳から受給可能です。
オランダ
全居住者が加入義務を持ち、受給開始年齢は67歳(2024年以降毎年8ヶ月のびる予定)です。
最低加入期間の定めはありません。
年金額は居住期間に基づいて年金額が決定され、全ての居住者に対して均等な給付が行われています。
2.共通する問題点
多くの先進国では、以下の共通した課題に直面しています。
・少子高齢化:出生率の低下と平均寿命の延びにより、年金受給者が増加し、支える現役世代が減少しています。
・財政負担の増大:高齢化の進行に伴い、年金給付額が増加し、財政的な負担が増加しています。
・制度の持続可能性:現行の年金制度を将来的に維持するための改革が求めれています。
日本だけでなく、各国はこれらの課題に対応するため、受給開始年齢の引き上げや保険料率の見直し、私的年金の導入・拡充など、様々な改革を進めています。






